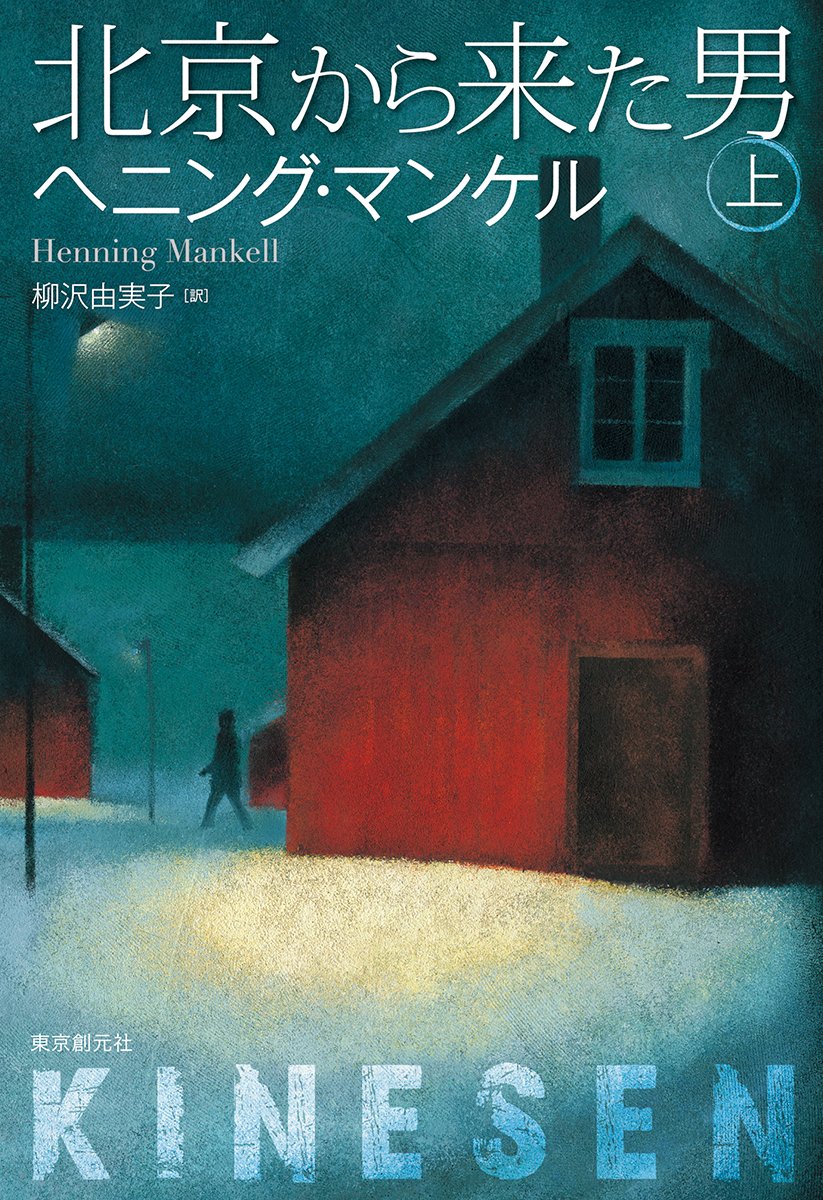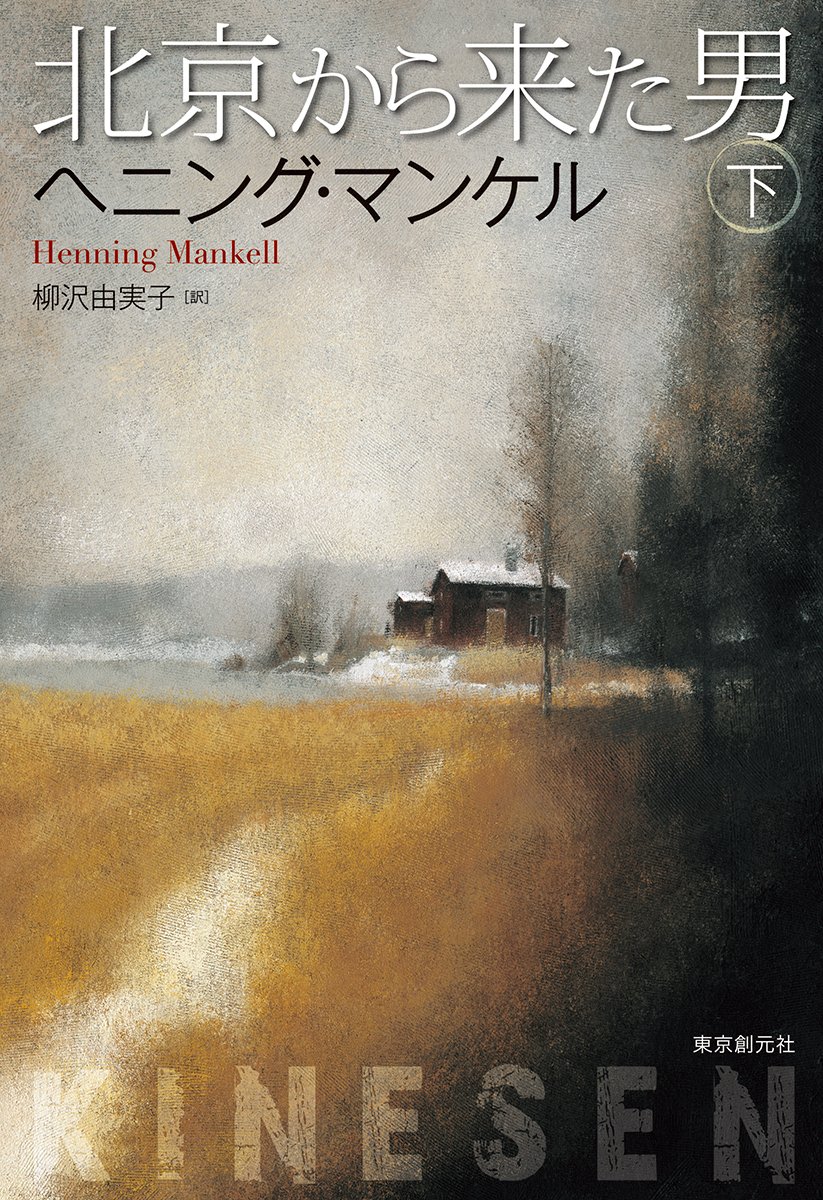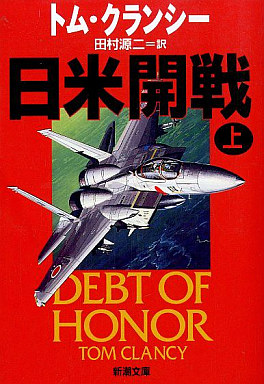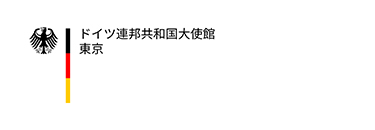単なる傑作よりも「問題作」を選ぶ日! の巻

2015年、いまさらですがあけましておめでとうございます!
さてさて前回の北欧ミステリーフェスリポートにて予告したとおり、新春初回の本稿、お題はスウェーデンの巨匠、ヘニング・マンケルの『北京から来た男』です。
スウェーデンの寒村で、ある厳冬の日、一晩のうちに村人のほとんどが惨殺されるという怪事件が発生した。周囲となんの諍いもなく平和に暮らしていた村が、なぜ壊滅させられたのか? 犯人は誰? そしてその動機は…?
で、タイトルから見てわかるように、ここに躍進する現代中国がからんでくるわけですね。
しかし、同じスウェーデンでもストックホルムやマルメといった国際都市の近辺で中国がらみの問題が発生するならまだわかるけど、それが、いったいなぜ人里離れた田舎の村で…? という部分が物語の大きなポイントとなるのです。
この作品は彼の有名なヴァランダー警部シリーズには属さない独立長編ですが、ドイツ語版出版時(2011年)、とにかく「あの」マンケルの渾身の新作! ということで、本書『Der Chinese』はドイツのどの書店でも山積みになっていました。話題度・期待度・露出度いずれも満点。そして肝心の評価は…ものすごく分かれました。それはこのドイツAmazonレビューの評価分布を見ればわかりますね。
皆様ご存知のとおりAmazonの読者レビューといえば、観点の質のばらつきがけっこう激しく、個別の内容を完全に真に受けるのはちょっとどうかな? という面はあるものの、特にレビュー数の多い作品の場合、そこに何らかの傾向を読み取ることは可能です。たとえば本作の場合…
【肯定派の意見】
●通常のミステリの枠を超えた領域に巨匠マンケルが至った。この「歴史と文化」を結びつける挑戦は素晴らしい!
●物語の中盤で展開される、キーマンとなるひとりの19世紀の中国人の生きざまを描く部分が、それ自体歴史小説のようで興味深い。
●「中国」というキーワードを介し、19世紀アメリカと21世紀アフリカをつなげ、その「人間の宿業」の連続性を描いたマンケルの筆致は見事だ!
【否定派の意見】
●中国をメインテーマとした割には、その理解がどうにも表面的に見える。いろいろな面で従前の作品に対し異質な要素に挑んだことが裏目に出たのか、ヴァランダー警部シリーズで見せたような問題提起の鮮やかさが感じられない。
●構成のバランスが悪い。たとえば中盤、中国人の一代記を描くパートが冗長な一方、後半の謎解きが性急で中途半端なのが気になる。
●物語の精神的背景として現代中国の問題を描こうとしていながら、どうも筆者の認識のベースは「毛沢東ブーム」周辺らしいので、最新情報で武装している割には根本的な陳腐さが感じられる。あとアフリカ贔屓がちょっと…
…と、こんな感じです。
私としては、どちらの言い分にも納得です。
そして、レビュアーがみんな心をかき乱されているように見えるのが印象的です。賛否両派とも、「いつもながらのマンケルで素晴らしかったですね」ではない感じ。実はこの点が重要だと思うのです。単なる傑作よりも「問題作」のほうが、えてして有意義な議論のタネになるのです。
ちなみに、私が本書についてどう思うか、といえば…
一切の前提を抜きに「この小説単体だけ」で評価した場合、構成バランスとか登場人物(特にロスリン判事)の行動の微妙な不自然さ等が気になるので、「うーんちょっとこれはイマイチ」となります。しかし、「どのような文脈でこの小説が書かれたか」を物語の一部として評価すると、逆転現象が発生して「うーんちょっとこれは傑作!」となります。
そう言うと、「え? それは変だ。予備知識や前提が必要だなんて小説として邪道でしょ?」と思われる方もいらっしゃるでしょうけど、マンケルのようなビッグネームならばある程度は許されると思います。それが社会的存在感・影響力の蓄積というもの…少なくとも、ドイツの文脈ではそう主張できるはず!^^
そう、重要なのは、「なぜこの小説はこうなったのか?」です。
マンケルが本書を執筆した動機は、彼が愛するアフリカ(具体的にはモザンビーク)に中国の開発資本が押し寄せてきたのを目の当たりにし、その戦略的かつ有無を言わせない雰囲気に、「これは形を変えた帝国主義・植民地主義の復活ではないか?」と脅威を感じたことなのだそうです。
つまり、メインテーマである「中国」に対する愛が根本的に無いというか、まあ、それは経緯からして仕方ないんですけど、良くも悪くもそういう一面があります。
以下ネタバレかもしれませんが、書物の意味と意義を有効に紹介するためには不可欠に感じられるので敢えて行きます。小説単体をあくまで純ミステリ的な文脈で楽しみたい方は読み飛ばして下さい。
本書は時代と世代を超えた一種の復讐劇で、その動機についての、「現代先進国のスタンダードな価値観から見た」際の不可解性が、物語の真の主題となります。
で、その不可解性を読者にとって可能な限り理解可能なものとするため、背景事情の描写を大過去にさかのぼって綿密に丁寧に行うのです。確かに中国人の流儀は根本的に異質すぎるように感じられるけど、実は彼らには彼らなりの道理と言い分があり、巨大な強迫観念とともに良識も存在する…というビジョンがそこから立ち上がってくる仕掛けです。が、しかし読み方によってはまさにその点が「冗長」と受け取られるのですね。
このあたりをトータルで「興味深い比較文化的チャレンジ」と感じられるかどうかが、作品に対しての評価に直結しているとも言えるでしょう。
そしてもうひとつ、不可解性が高いゆえに「欧米の論理」だけでは事件全体の実証立証が困難で、ゆえに、ある登場人物の憶測によりドラマのキモとなる部分が補完されて完結する、というのが本書の大きな特徴です。
これは「不可解」「不可知」の存在をリアルに体感させるにあたって非常に効果的な文芸的ギミックだと思います。しかし他方、純ミステリ的な観点からは違和感が残るというか締まりが無いというか、何かしらの批判を誘発しそうに感じられます。
総じて本書は、「きわめて高い能力と社会的影響力を自覚している作家が、使命感をもって、愛を感じにくい対象への分析・問題提起を行おうと誠実に努力した」ことの結果として、大変興味深い事例になっていると思います。ミステリとしても一般文芸としても、そのような観点から読み解き、もし可能であれば読後に議論するのが本書のポテンシャルを最大限に活かす道だろう、というのが自分の実感です。
以上はドイツ人読者としての見解です。では日本の読者はどうなのか?
あくまで一例ですが、日本人の知人から聞いた本書のインプレッションをここに記してみます。
* * * * * * * * *
欧米世界の常識の範囲外からの「復讐」をアジア人がぶちかましてくる、という図式は、ある意味トム・クランシーの『日米開戦』に似ている。読者層がたぶん何気に違うから『北京から来た男』と直接比較される機会は少ないだろうけど、ここには一種の相似形がある。つまり、欧米から見たアジア文明の不可解さ・怖さの根源イメージのひとつに「世代や時代を越える儒教的な執念深さ」があるのかもしれない、という気がしてちょっと興味深い。
但し、人物の行動動機の納得感という意味では、「トンデモ」と批判された『日米開戦』のほうが妙に優れていた気がする。これはトム・クランシーが、敵役に据えながらも日本に対して前向きな関心を持っていたからではないだろうか。『北京から来た男』はその点がツラいというか、内容の割に記述が長い印象が拭えない。
これについてマライさんは「彼らには彼らなりの道理と言い分があり、巨大な強迫観念とともに良識も存在する」ことの説明になっていると述べていて、まあ確かにそうなのだけど、それを行う中国人キャラクターの人物造形が(正のヒトも邪のヒトも)どうにも類型的に見えるので、その点がちょっと残念かなと。
『日米開戦』は日本人から見て、こういう日本人キャラは非現実的だ! と言い切れないまでもまあ普通じゃないよな、という印象だけど、ベストセラー作家がこういう書き方をしたために、「日本人ってこうなんだ!」と思い込む残念な読者が彼の地に増えたという話があって困った、というのが実感。
『北京から来た男』を中国人が読むとどう感じるのだろう? マンケルは本書を書くに当たって、よき中国人ブレーンの協力を得られたのだろうか?
* * * * * * * * *
なるほど。いろいろ参考になります。
特に最後の「中国人が読むとどう感じるのだろう?」「本書を書くに当たって、よき中国人ブレーンの協力を得られたのだろうか?」というのは私もひそかに気になっていた点であり、実際にはたぶん今後の業界的課題として作家と批評家に課されてゆくのだろうな、と思います。
…と、以上、今回は単に読書の味わいで完結するのではなく、大きな観点から議論しないともったいない本のご紹介、およびその知的好奇心のツボを刺激する試みでした。
ちなみに次回のお題は、日本版が今月出版されたばかりの、あのフェルディナント・フォン・シーラッハの『禁忌』の予定です。この作品もドイツで評価真っ二つの激論を巻き起こした問題作。そして今回以上に「なぜこう書かれたのか?」というメタ性が強いため、邪論に至るかもしれない分析にご期待ください!(笑)
ちなみに2015/1/22(木)、東京ドイツ文化センターで開催される「ドイツ・エンターテインメントの夕べ」はまさにその『禁忌』特集。翻訳者・酒寄進一さんがいつもながら驚異のフルパワーで語りつくす予定なので、皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。入場無料・千客万来!
ではでは、今回はこれにて Tschüss!
(2015.1.17)

© マライ・メントライン
マライ・メントライン
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。