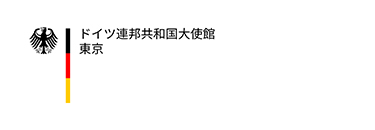ベルリン警察ミステリ、驚きのクロスカウンター!

前回の記事で、ついに登場した「本気ドイツ人作家」の戦前ベルリン警察ミステリ、フォルカー・クッチャーのゲレオン・ラート警部シリーズをオススメしました。
あの勢いからすると、「これまでの英米作家によるベルリンものを凌駕した!」という言葉がついつい口を突いて出てきそうですが…
本当にそうなのか? そう言えるのか?
そこで今回は敢えて米国代表、私がミステリマガジンの「洋書案内」でも言及した米国作家ジェフリー・ディーヴァーの作品、『獣たちの庭園』(2004年)を取り上げてみようと思います。
ディーヴァーは、世界の首都NYを舞台にした科学捜査サスペンス「リンカーン・ライム」シリーズで有名な作家です。中でも『ボーン・コレクター』は、映画化されてアンジェリーナ・ジョリーのブレイク作となったことでも著名ですね。
彼の作品は、どんでん返しと緻密な論理の大胆で絶妙な組み合わせ、そして、いい感じのスピード感が特徴です。まさに今風のサスペンス作品を象徴する存在といえるでしょう。実際、『CSI』や 『クリミナル・マインド』といったその手の2000年代の人気ドラマは、ディーヴァーという元祖が居なかったらそもそも存在しなかっただろうと思われます。
現代のNY市警を舞台とするならば最高の作風。そして、その筆が戦前のベルリンを描くとなると…
『獣たちの庭園』の舞台は1936年、オリンピック開催を控え、祝賀気分に華やぐ第三帝国の帝都ベルリン。
そのベルリンに、米軍上層部の密命を帯びたNY暗黒街のヒットマン、ポール・シューマンが潜入する。彼はドイツ系でドイツ語が堪能なため軍に目をつけられ、半強制的に雇われたのだ。彼の使命は、ドイツ再軍備強化のキーマンとなっているある人物を抹殺すること。しかし、その潜入はやがてドイツ側に察知され、ベルリン刑事警察きっての敏腕捜査官による執拗な追跡が開始される…
…と書くと、なんかすごい「ありがち」感に満ちてるでしょ?
実際、途中まではナチ突撃隊によるリベラル系書店の打ち壊しとか、それを見て義憤にかられた主人公が介入してピンチに陥るとか、ナチス首脳、特にゲーリング(ゲー様!) の強欲俗悪っぷり描写とか、なにやら「これってどこかの歴史ドラマで見たよね」的な情景が目につきます。そこで、正直、まあこれが米国の今どき人気作家の限界なのかなぁ、などと思いながら読み進めたのですが…なんと!
それらのステレオタイプ的描写そのものが、実は、「物語の真の姿」を隠す目くらましに過ぎないのです。なので、たとえ嫌気が差しても、途中で読むのをやめてはいけません!
物語中盤、主人公を追う敏腕捜査官のヴィリ・コール警視が、学校や近所づきあいを通じて進行する息子のナチ化を憂い、それをなんとか押しとどめようと必死に心を砕く場面があります。表面的にはメインストーリーに絡まない単なる余話、エピソードとして扱われる箇所かもしれない。が、たぶん本当は違う。絶対に違うのです。
この感触をたとえるならば、どこに通じているのかわからないドアが視野の隅にさりげなく出現した、みたいな感じでしょうか。そしてこの場面以降、暗殺サスペンスとしてのメインストーリーの背後で、「絶対悪とは、純粋悪とは何か?」という観念的な追求が地味にうねりはじめます。この両者は絡みあい、そしてクライマックスで激しく融合するのです。
ディーヴァーには、「どんでん返しの達人」という渾名があります。いわゆる「A氏が真犯人かと思ったら実はB氏でした!」的な技を極めたもので、通常、それは叙述ギミック以上の意味を持たないはず。しかし彼は『獣たちの庭園』にて、エンタメ的な材料を駆使しながら、歴史観念レベルの「どんでん返し」をみごとにキメてゆきます。
その結果、主人公は、「ナチの組織に君臨して悪徳をむさぼっている誰それ」ではなく、「ナチズム原理の一つそのもの」をモーゼル小銃の照星にとらえてしまうのです。そしてその状況は、単に目標を撃てばよいというのではない、究極の選択を主人公に強いてきます。これには驚きました…まさかここまでやってくれるとは。恐ろしい筆力です。
本作に対するありがちな否定的評価に、「冷徹な狙撃プロフェッショナルであるはずの主人公が、クライマックスの肝心な場面でつまらない動揺を見せるのが変だ」というのがあります。はい、それはよくわかります。普通に今どきっぽいサスペンスを期待して読む人にとっては確かにそうでしょう。
しかし、ナチズムの本質について真に知的関心を持つ読者なら、「ナチズムとは一体なんだったのか?」「もしもユダヤ人差別さえ無かったら、ナチはどう評価されたのか?」といった領域に思考をめぐらせた経験を持つ読者なら、あのクライマックスの持つ意味の深さに頭脳センサーが激しく反応するはず。かの、『極大射程』の狙撃王ボブ・リー・スワガー でさえ直面しなかっただろう巨大な難局が主人公を締めつけているのが「見える」はずです。
そこにこそ本作の真価がある!! と私は力説したい。
ときに。
ストーリーだけ見れば、この物語でベルリン刑事警察は脇役・敵役に回りそうです。しかし私が敢えて「ベルリン刑事警察ミステリ」の称号を本作に冠するのは、ヴィリ・コール警視という登場人物の、物語の枠を超えた存在感と生命力、そして精神性の見事さゆえです。読めばわかるように間違いなく彼は「もう一人の主人公」であり、いつも比較的クールな作者が、特別に気合を込めて生んだキャラクターであることがうかがえます。
いささか皮肉な言い方になりますけど、ドイツ的な社会生活情景が地元作家に比べ薄味だからといって、私は彼を前回オススメしたゲレオン・ラート警部の下位には置きたくない。これは単なる感情論ではなく、コール警視とその周辺の捜査官、そして「敢えてフィクションとして」刑事警察本部に置かれたDeHoMagカード選別マシンなどの描写が、ドイツ人とドイツ組織のありようを、ドイツ人作家とは違う観点でそれなりに的確に照射しているように思われるからです。
『獣たちの庭園』は、コール警視と狙撃者シューマン、それぞれのモノローグによって終結します。これが非常に泣けます。コール警視が「捜査官として」「人間として」の使命感を、シューマンが「アメリカ人として」「ドイツ人として」の使命感を両立させようと死力を尽くした、その結末が述べられます。このように書くとネタバレとかなんとか言われるかもしれないけど、構いません。大丈夫です。そんなことで揺らぐようなヤワな作品じゃありません。とにかく読んでみてください。
私の場合、読んだ後30分ほど、脳細胞のスタンディングオベーションが続いておりました。
この小説はエンタメとか文学とか、そういうジャンルカテゴリーの重力を超越したナニカを持つ逸品です。「ドイツ者」的には万全のオススメです!
【P.S.その1】
ディーヴァー先生は、「ビジネスとして、契約として」長編小説を1年サイクルで執筆すると決めているそうです。が、『獣たちの庭園』の場合、そのルールを逸脱して2年の準備期間をかけたそうです。冒頭の「献辞」の重みも他の作品とは違います。ひょっとして本作は、彼にとって採算度外視の「入魂作品」なのかもしれません。
【P.S.その2】
「人情派ベルリン捜査官」ヴィリ・コール警視がこの単発作品だけの登場となるのは惜しい! 単発なのにシリーズものに匹敵する存在感があるといえど、やはり惜しい…(ゲレオン・ラート警部は8巻予定だし、フィリップ・カーのベルニー・グンターものは4巻あるし!)…と思っていたのですが、実はなんと、本作はあの「リンカーン・ライム」シリーズの「エピソード・ゼロ」という位置づけにあったりします。ある箇所をよく読めばわかります。コール警視の曾孫は、外見こそ似ても似つかないけど、曽祖父の愚直な道義心をしっかり受け継ぎながらNYの街を疾走するのです。なので、もし本作を読んでみてお気に召したら、ぜひ『ボーン・コレクター』を読んでみてください。たぶん後悔はしません!(笑)
【P.S.その3】
ある意味、私がいちばん納得できないのは、ジェフリー・ディーヴァー大人気で、ほぼ全ての作品が訳されているドイツ(Amazon.deでの 『ボーン・コレクター』のレビュー数と評価を見よ!) にあって、なぜか『獣たちの庭園』が未訳(2012年9月時点)という点です。これは不自然だ。何故なんだドイツよ!! 「真に悪いのはナチなのかドイツなのか?」の核心に迫るあのオチがあまりに痛いところを突いているためなのか? 困ったものだ。翻訳家たちよ、ぜひ、このいけない現状をなんとかしてください!
それではまた、Tschüss!
(2012.10.01)
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)