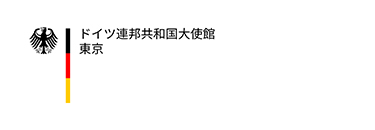なぜ、ネレ・ノイハウスが「大本命」なのか?

2012年6月、東京創元社から ネレ・ノイハウスの『深い疵』が出版されました。ノイハウスは、男女2人組の捜査官を主人公とする「オリヴァー&ピア」シリーズの作者で、私が邦訳ドイツミステリの「大本命」と目している作家です。『深い疵』日本語版の帯に、「ドイツでシリーズ累計200万部」とあるのが目をひきますね。私はドイツの書店でその売れ行きと存在感を目の当たりにしていたので、感慨もひとしおです。いろいろな思いが湧いてきます。
そこで今回は、なぜ彼女の作品はそこまで売れたのか? 何が画期的だったのか? という点について、ちょっと掘り下げて考えてみたいと思います。
ネレ・ノイハウスの「オリヴァー&ピア」シリーズの秀逸さについて。
たとえば翻訳者の酒寄進一さんは、欧州ハブ空港都市フランクフルトに隣接した「タウヌス高地」という、ワールドワイドなテーマにもローカルなテーマにも対応できる絶妙な土地を舞台に設定したこと、そしてドイツ固有の(ただし諸外国でも認知度の高い)社会的テーマを的確に取り上げる目のつけどころの鋭さといった要素を、訳者あとがきの文中で挙げています。私もこの見解にまったく賛成です。
また、ドイツ人読者である私の視点からは、「ドイツ人のリアル関心・欲求にストレートに訴えかける」日常描写の効果を追記しておきたいです。
ドイツ人作家が知的に気合を入れてエンタメ作品を書く場合、なぜか舞台が唐突に南欧へ飛んだり、あるいは、ドイツが舞台であってもキャラクターなど妙に無国籍っぽい雰囲気で話が進んだり、という現象がよく見られます。ドイツ国内の読者にとってはそれでよいかもしれないけど、海外の読者からみるとけっこうな違和感、さらにいえば「はぐらかされ感」が生じかねません。また逆に、最初からドイツ国内地元ネタ・地域くささで勝負するタイプの作品(いわゆる「ご当地ミステリ」など)は、その地域市場だけでウケが取れればよいと割り切って書かれるせいか、質的にかなり物足りなさを感じてしまいます。
ネレ・ノイハウスはそのどちらでもありません。強いて言えば、「ご当地ミステリを才能とセンスのある作家が真摯に書けば、これほどのことがやれるんです!」という、既存業界のしきたりを突き抜けた存在のように見えます。
彼女の文中には、ドイツ人なら「ああ、それあるある!」と感じずにいられないリアル生活感、そして…どちらかといえばこちらのほうが重要かもしれないが…貴族社会、お屋敷、乗馬といった、昔からドイツ人の日常感覚に強く定着している「上流志向」趣味的な要素が、実に巧みにアレンジされながら登場します。
たとえば主人公の一人、女性警部ピア・キルヒホフは乗馬を愛しているのですが、颯爽とした乗馬シーンなどまったく無く、生真面目に厩舎の馬糞掃除ばかりやっています。しかし実はそれが素晴らしい。メロドラマの一場面みたく馬をカッコよく乗りこなすよりも、愛情をもってきちんと馬のめんどうを見る人間のほうが遥かにカッコイイ! という、通俗的な文脈を逆手に取った表現なのです。さすがです。
…しかし、書きながら気づいたのですが、ここまで本稿で挙げてきたのは、あくまで「作品の面白さを支える」要素です。言い換えれば、それらを機械的に揃えただけで面白い小説ができるわけではありません。ネレ・ノイハウスの小説が、私を含めドイツ読書人の心をひきつけた根本的な理由は何か別にあるはずで、それは一体何だろう? あくまで私見ですが考えてみました。
ノイハウスの小説の主人公、オリヴァー・フォン・ボーデンシュタイン主席警部とピア・キルヒホフ警部は、ある共通性を軸に強い仲間意識をもっています。それは、「頭が切れる割に欲が深くない」ということです。
ドイツの場合、頭の切れ味と欲の深さはだいたいセットになっていて、というかそれを既成事実化したがる人が多く、結果的に、強い論理的自己主張をやった者が場の権利を奪う傾向が強いです。そういう意味で、オリヴァー&ピアの立場はかなりつらい。つまり、その能力と成果が、慢性的に不当に報われない状況に置かれてしまいがちなのです。
作中で彼らは、犯人と戦う以前に、常に「ドイツ的な欲深さ」と戦っているといえるでしょう。そして、欲深く強烈な権利意識を持つのが、必ずしも悪の側ばかりとは限らないのがミソであり、濃厚なドイツ的個性であり、本作の人間観の魅力ともいえるだろうと思います。
オリヴァー&ピアは、率直にみて「ドイツ人社会」そのものに頭を押さえ込まれて苦労しています。が、彼らの特性や能力を最大限に発揮できるのは「ドイツ人社会」しかありえない、という逆説的な真実もあります。
「ドイツ」は彼らを見下したがるけど、逆に、無自覚ながら真に彼らを必要としている…この矛盾から主人公の内面にわきあがってくる「欲得抜きの闘志」みたいなものこそ、私はノイハウス警察小説の魅力の核心のひとつではないかと踏んでいます。
これはまさに、いろいろな意味で「ドイツ」を看板とするに値する個性でしょう。だからこそ、私は日本でこの小説を紹介したいと思うのです。たとえば、ドイツ文化趣味業界に属している方々には「いまどきの警察ミステリの面白さ」を、ミステリ業界に属している方々には「いまどきのドイツ実情の面白さ」を、それぞれ知っていただけたらとても素晴らしい。それは、もともとの関心事項についての知的価値を、何倍にもパワーアップさせるきっかけになりうるからです。
と、まあ、いろいろドイツ人っぽく論理的に語ってしまいましたが、きっと日本にも潜在的に存在したであろう、「ドイツの警察サスペンスというからには、こういうのを読みたかった!」というニーズに、本書が120%きっちり応えてくれそうだということ、それがまずは嬉しいのです。ぜひ手にとってご覧ください!
それではまた、Tschüss!
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)