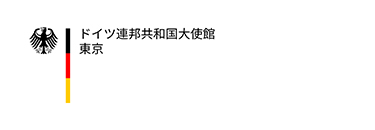いま敢えて、「宿敵」を語る。

以前マライ・de・ミステリ3のインタビューにて、翻訳者の酒寄進一さんがシーラッハ『犯罪』の本屋大賞受賞について、「ようやくランキングで1位をとれたっていうのが…」と感慨深げに語っていたのを記憶している方もいらっしゃるかと思います。
そう、『犯罪』は、2011年の年末恒例ミステリランキング「このミステリーがすごい!(宝島社)」、「週刊文春ミステリーベスト10(文芸春秋)」、「ミステリが読みたい!(早川書房)」ですべて2位だったのです。
名だたるランキングでオール2位ならば、どれかひとつで1位をとるよりもひょっとして良いんじゃない? 安定した高評価の証明なんだからさ、という捉えかたもあるでしょう。しかし問題は、上記ランキングでことごとく、アメリカ製の小説『二流小説家』が1位をゲットし、「初のランキング三冠達成!」として翻訳ミステリ界の話題をさらってしまったことです。
これはなんだか微妙に口惜しすぎます。あと一歩のところで常にルパンに逃げられてしまう銭形警部のような気分。良質のドイツ小説の受容発展を願い、翻訳出版のはるか以前からシーラッハに注目していた私から見れば、『二流小説家』はまさに目の上のタンコブのような存在です。やっぱりなんだかんだいって英語圏がミステリの中心だからこういう結果になってしまうのか、とか、早川書房が出しているランキングだから早川の作品がトップになってしまうのか、とか思ってしまうのですよ。もしも逆風的な条件が無ければ、純粋に作品の内容だけで勝負すれば、絶対にシーラッハの『犯罪』こそが「三冠」にふさわしい…に違いない!
この「違いない」がクセモノですね。たとえ内容に絶対の自信があるにしても、憶測だけで断言し、結論を出してはいけません。そこで、「宿敵」のニクいアイツを読んでみることにしました。
その結果は、驚くべきものでした。
デイヴィッド・ゴードン『二流小説家』は、事前の予想通り、まさにアメリカ流(というイメージ定義も読者により多少のブレ幅があるのは知っているが、敢えてそう言いたい)のノリ、展開、登場人物で構成された作品です。Howdunit(How done it)を軸とした「ミステリ」としての作品構造も、まあミステリを読み込んだ人間から見ればオーソドックスな範囲のものといえるでしょう。
そして予想外だったのは、それらすべてのアメリカ的文脈が、意図的に「舞台の書割」のような存在として配置されていることです。ゆえに作品の終盤に展開される、「類型」の世界に満足してしまいがちなミステリ業界マインドへの疑問提示が、最高に鮮やかに決まるのです。
「ぼくはつねにひとつのジレンマを抱えていた。どうしても結末よりも始まりが好きだいうことだ。推理小説を愛すればこそ、謎が解きあかされることに漠然とした落胆を覚えてしまうのだ。推理小説を書くにあたっていちばん厄介なのは、虚構の世界が現実ほどの謎には満ちていないという点にある…(中略)…だからこそ、ぼくは大半の推理小説に落胆してしまうのだろう。そこに示される解答が、みずから蒔いた途方もない疑問に答えているとはとうてい思えないからだ。」(日本語版P.449より)
確かに『二流小説家』は、純ミステリとして「も」面白い。最高水準の作品です。しかしおそらく、この小説の真価をそこだけで測ってはいけない。「現実とはそもそも何なのか?」という領域をかすめながら、「なぜ読書人は、限界や制約にまみれた『ミステリ』という箱庭世界をほじくり返し続けるのか?」という嘆きに似た考察が語られる終章、あの枯れた美しさを味わってほしい。どうせ感想を語るならあれを踏まえた上で語ってほしい、と思うのです。
そして、ここでデイヴィッド・ゴードンが提示する意識には、図らずも、フェルディナント・フォン・シーラッハがクライスト賞の受賞スピーチ で語った内容と強烈に通じあうものを感じます。小説という「現実の再構築」に読者は何を希求するのか? 小説は果たして現実の何を補完するのか? …出版当初、『犯罪』を文学的に無価値と断じた堅物な批評家たちに対し、シーラッハが皮肉と誇りを込めて定義した「文学の対極」という観念を、実は『二流小説家』が何かしら共有していたのです。これは私にとって驚きでした。この両作品は、実は対立するのではなく、内面的には驚くほど「寄り添って立つ」存在だったのです。
シーラッハの『犯罪』は、いろいろな異論はあれど、「ミステリとしても読める」文学、という評価が一般的なようです。ゴードンの『二流小説家』はその逆、「文学としても読める」ミステリといえるかもしれません。そしてその文学性によって権威っぽくふるまったり格好つけたりせず、読者の期待や予想を超えた高度な内容を提供している、という点で両者は共通しています。
こうしてみると、当初の先入観とは正反対に、「天才」シーラッハの猛追を受けながら、そしてアンチミステリ的な含みを放ちながら、よくぞ『二流小説家』はミステリ界のメジャーランキング三冠を達成した! と思わずにいられません。ものごとにはいろいろな側面があるのだなあ、と痛感します。
シーラッハの世界の奥底にシビれた人にこそ、敢えて『二流小説家』をオススメしたい、というのが今回の結論でしょうか。シーラッハとの内面的な「縁」だけでなく、ジャンル小説としての「ミステリ」の今後の身の振り方を考えさせられる点でもオススメです。そういう意味でドイツミステリ「業界」としては、たとえばフィツェックさんには少なくとも今の3倍ぐらい「脳力」を発揮してもらわないとなー、などと勝手なことを思ってしまったり。
ドイツ作品だけ見ていては、「ドイツミステリ」は語れないのです。
それではまた、Tschüss!
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)