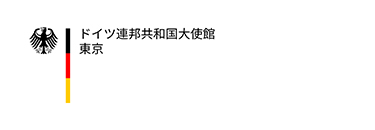ミステリ不毛の大地に立つ !?

「ドイツ」のミステリ・サスペンス小説、と聞いて何か思いつくでしょうか? たぶんムリだと思います。伝統的にエンタメ領域が軽んじられ、文才が圧倒的に「文学」に投入される状況では、ルパンやホームズや名探偵コナンのような「国際的文芸スター」は登場できなかった・・・・しかし今、そんなミステリ過疎地帯に化学変化が起きつつある ! というドイツ文芸事情のあれこれを綴ります。よろしくです。
たとえば「ドイツが誇る名探偵」というコトバを書いてみる。
…と、わずか9文字なのにすごい違和感が生じます。日本的な感覚で言えば、「きれいなジャイアン」に近いものがありますね。笑えて悲しい現象というべきか、実際、ドイツ人にとっても「名探偵」といえばホームズやミス・マープルであって、対外的に誇れる国産の名探偵はまるで思いつきません。
なんで ?
ドイツといえば、緻密な論理性を重視するお国柄。
ならば世界的な名探偵キャラの1人や2人ぐらいは居てもよさそうなのに、文学文芸領域で目につくのはツァラトゥストラとかヴィルヘルム・マイスターとか、「生きるに値する人生とは何か?」といったタイプの「謎解き」を追究する人ばかり!
ドイツ社会には、哲学的な命題こそ論理的思考力を活かすための「メジャーリーグ」であって、ゆえに密室殺人みたいな話は全力投球に値しないからお呼びでない、という固定観念が伝統的に存在するんです。なんということだ。
密室殺人にしても、それだけを見るのではなく、事件を取り巻く集団心理・社会心理といったものにも目を向ければ、やりようによってまさにメジャー級の知的興奮に至ることができるんですけどね。ドイツ文学界はそういう道を選ばなかったのです。
その姿勢によって得たものは確かにあるけど、失ったものも決して小さくはない。この間読んだ英国人作家ケイト・サマースケイルの “Der Verdacht des Mr Whicher” (邦題『最初の刑事』) のような出来のいい記録文学を読むと、その「失った小さくないもの」の蓄積を強烈に実感させられます。これはつらい。
こんなふうにドイツは、上質の知的エンタメを国産化しづらい体制を自分でつくりあげてしまったのです。が、当たり前といえば当たり前なことに、その手の作品を求める読者ニーズはドイツにもしっかり存在しました。そこで昔の映画業界と同じように、基本的に輸入でまかなうことにしたのです。輸入元はいうまでもなく英米です。ときに英米のエンタメ作品というのは、ステレオタイプイメージを「お約束」として効果的に活用して成立する傾向があって、その中で「ドイツ人」は、
・頑固
・冷酷
・マッドサイエンティスト
・ナチ
という属性が与えられています。リアルドイツ人から見るとずいぶんひどい話なのだけど、作品世界の完成度が高くて一般論的な説得力も強いため、不満があっても正面からなかなか対抗しづらいという「物語的現実」があります(そういった描写をむしろ楽しむ、というマゾヒスティックな道もありますが)。
そして、この状況が慢性化したことが、ただでさえ日陰の身だったドイツ国産エンタメ作品の発達をさらに阻害したように思います。つまり、英米作品を
・不器用に真似る
・過度に無視する
・否定してアンチテーゼに走る
といった感じになってしまい、根元に巨大な不完全燃焼を抱えたまま進まざるを得なかった面があります。ある意味、自分のポテンシャルに対し無自覚に呪いをかけてしまっていたといえるかもしれません・・・。
この長年の悪循環に歯止めがかかるきっかけが起きたのは、1990年代初頭のことです。それは何だったのかというと・・・語ると長くなるので、このへんの話は次回に !
* * * * * * * * * * * * * * *
ちなみに東京創元社のミステリ専門誌『ミステリーズ !』 51号(2012.2.12発売)はドイツミステリ特集で、いまドイツで大人気のフェルディナンド・フォン・シーラッハを大きく取り上げています。シーラッハの『犯罪』は、『このミステリーがすごい ! 2012』の海外編で、英米の強豪作品たちを相手に堂々の2位をゲットし、日本の翻訳ミステリファンに衝撃を与えた傑作です。
『ミステリーズ !』誌上では、『犯罪』の翻訳者である和光大学教授の酒寄進一先生と私の対談記事があったりしますので、ご興味があれば手にとっていただけると幸いです。ひょっとして、このエッセイで今後取り上げる話題を先ばらししているかもしれませんが・・・まあ、細かいことは気にせず書くことにします !(笑)
それではまた、Tschüss !
(2012.02.03)
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)