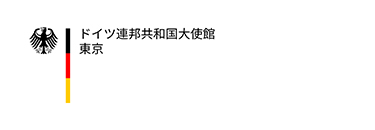『ドイツでの働き方、日本での働き方 パート3』

今回のテーマは『ドイツの働き方、日本の働き方 パート3』です。
今回お話を伺ったのは現在ベルリンのシャルロッテンブルグ地区にある日本料亭『893』で調理人として携われている渡正穂さんです。このお店ではオープニングスタッフとして立ち合われ、それまでもミュンヘンの日本料理レストランで調理に関わられてこられた方です。
日本で調理師学校を卒業された後、ドイツには就職で来られ、現在までドイツの食文化に関わられてこられました。
好きではない料理を仕事にする術や日本とドイツの食文化の違いについてお話を伺えるということで、イーストサイドギャラリー近くのカフェに出向きました。
今日はよろしくお願いします。まずドイツに来られた経緯を簡単に教えていただけますか。
『1990年代にドイツに「大都会」って日本料理のレストランがあったのご存知ですか、キッコーマンの経営なんですけど。料理をすることに興味はなかったんですけど、調理師学校を卒業する際の就職活動で海外で働ける就職先ということでいいかなと思って、就職と同時にドイツに来ました。』
就職きっかけなんですね。
『外国に対しての憧れみたいなものもありましたし、3年間の契約だったし行ってダメだったら帰って来ればいいやっていう軽い気持ちで。今思えば先のこととか何も考えてなかったんだと思います。ただ格好をつけてたのもあったと思います。』
ドイツに対して何かしら思いがあって来られたわけではなかったんですね。
『特別に強い思いはなかったです。ドイツでしばらく生活を始めて気づいたのがドイツ人と日本人とよく似てるねって言われるけど、それも違うなと。全く日本人と違う人種というのもわかりました。こちらに来てみてドイツは日本にいるときよりも意外と息苦しくない感じがしました。』
ドイツに来る前と来てからだとドイツやドイツに暮らしてる人々に印象の違いはありましたか。
『悪い印象も無いし取り分け良い印象も無いし、結果的には僕にはすごく住みやすい国でした。合ってたんでしょうね。1995年に来た当時は週末にお店やスーパーは全て閉まっちゃう時代で。平日でも18時以降はどこもお店はやってないって状態でした。そういう面では不便はしましたけど、それ以外で特に不自由さを感じたことは無かったですし楽しかったですね。』
元々ドイツに来られて3年で日本に帰国される予定だったんですよね、現在までドイツで生活される経緯を教えていただけますか。
『当時ベルリン店で働いていた時の上司が昇進してミュンヘン店の調理長になったんですね、それでミュンヘン店の調理長に僕が呼ばれてですね、ミュンヘン店でもう少し頑張ってみないかと。その後は単年契約でミュンヘンで2年続けて。その後「大都会」を満期で終えた後ミュンヘンのベトナム人経営者の寿司バーに就職したんですけど、働いてるうちにそこで人種差別的な嫌な目にあいまして、「大都会」で働いている時も似たようなことがあってミュンヘン嫌だなあと思って。思い返すとベルリンの方が居心地が良かったなと気づいてベルリンに帰りたくなったというのがありました。それでベルリンの方で仕事が無いかなって探し始めた時に知人に話をしたらお店を紹介してもらって。それで今のレストランのボスと出会うことになるんですけど、流れとしては「大都会」ベルリン店、「大都会」ミュンヘン店、ミュンヘンのとある「寿司バー」、ベルリンのトルコ人経営「寿司カクテルバー」、現在のベトナム人経営の「寿司バー」ですかね。』
お話だけ伺ってると店は変わったけど転職はされてないですよね、働く環境は切れて無い。
『結局そういうことだと思うんですよ。モチベーションのひとつとして結局色々なところで必要としてくれる人がいたってことで、誘われてるとこっちも気分がいいじゃないですか。好きな仕事ではないにしても出来る仕事に就いたんだなっていう実感はありました。仕事に対しては僕は人から必要とされてるというのがモチベーションです、何をやってても。』
人と人との繋がりを大切にされているんですね。ドイツが好きで生活されているというよりは、就職の際に調理師が身近にあって、たまたまドイツに来られて料理の世界に関わられてる。
『そうですね。今のボスがそうですけど、必要としてくれる人がいたので続けて来れた感じです。』
学生の頃は魚屋で働かれてたんですよね。
『魚屋で働いている時は就職の内定をもらったビザ待ち状態で、ビザが発行されれば仕事を辞めることは事前に魚屋に伝えてあって。給料は安かったですけど料理の勉強が一番できたのはあそこですね。』
フットワーク軽いですよね。
『何も考えてなかったんでしょうね、ほんとに。魚屋さん以外のバイトも掛け持ちでやっていたのですが、例えばミスタードーナッツでもバイトしてました。』
時間のある時はとにかく働いてですか。
『全部埋めてましたね。日曜日は飲食とは関係ないバイトで遺跡発掘のバイトをやってました。おじいちゃん達に混じって測量行ったり楽しかったですね。』
ギラギラした若者というよりは何か堅実ですよね、外国に興味と憧れがあって就職され、半ば強制的に就職先のドイツに来られ抵抗感もなく馴染まれ生活されている。
『当時は偏見も先入観もなくすごくフラットな感じだったと思います。それは今もあまり変わってないですね。長く住んでるだけあってドイツ人との人間関係のしがらみや付き合いはあるので、イメージは多少なりとも変わったところはありますけど。』
そういうの大事ですよね。ありのまま受け入れるというか。
『高校生の時に勉強が全然出来なかったんですけど、唯一世界史だけは興味があって勉強は他の教科よりはしたんですけど、世界史で学ぶドイツ人像と実際のドイツ人とはあまり重ならなかった印象ですね。』
重ならなかったとは?
『世界史で学ぶようなドイツは第二次世界大戦の話が多いじゃないですか。ドイツ人は人種を迫害したとか、なんて冷たい人種なんだっていうのはあったんですけど。実際に来てみるとそうでもなかった。僕がドイツに来たのは1995年ですからベルリンの壁が崩壊して東と西が併合されて6年しか経ってない時なんですよ。当時の西の人たちは東の人達に対する差別っていうのは実際にはあったんですよ。お前はオシー(Ossi)だからと言う会話を聞いたことありましたし、職場でもライプツィヒ出身の同僚がいたのですが、秘書の方も東ベルリン出身でした。別の職場の東ベルリン出身の同僚と外に出かけた時に差別を受けてると感じる状況に遭遇したことはありましたね。』
世界史のイメージと似たような?
『世界史のイメージと似たようなものもありましたけど、教科書にのってるほどの冷たさではなくて。一方で同僚の秘書の方はすごく親切でしたし、なんて優しい人だろうって思いましたから、僕にとってはドイツのお母さんって感じでしたし良い印象ばかりでした。』
世界史の教科書は偏ってるって思われますか。
『日本も含めて戦争に負けた国同士ですし、日本もあまりよくは書かれないですが、印象操作されてるのかどうかは分かりません。』
歴史上ドイツは確かに酷いことをして、日本もそうですけど、語り伝える出来事は実際歴史上にあったわけですよね。
『実際に自分の目で見て、違いを自分なりに確かめられたのは良かったと思います。教科書に書いてることだけじゃない、実際に自分で体験して判断できた、人の口伝えのイメージは自分が経験した事とは違うことが分かったのは良かったと思います。』

これまで飲食に関わられてこられて、ドイツの食事情をどのように感じられたか教えていただけますか。
『最初にドイツ料理を食べた時の感想は、今まで食べたことのない料理の味という感想で、初めは美味しく感じたんですけど日本で言うご当地メニューみたいなものは、ドイツは日本と比べて少ないなと。食にはあまり興味のない人達なのかなというのが最初の印象でした。働いてるレストランでドイツ人の常連のお客さんが来ても必ず同じものを食べるんですよ。強く薦められない限り新しいものを試そうとしないんですよね。初めてレストランに来て美味しかったものを次回も頼む。その次もまた頼む。それが食べたくてこの店に来る。気に入ったものを頼み続ける。そんな印象です。例えば1990年代に大都会で働いていた時も今のレストランでもそうなんですけど、その傾向は変わってないですね。フランス人のお客さんみたいに、新しいメニューが出たらすぐにとび付くとかはしないし、食に対して保守的な人達が多いのかなという印象があります。自分がもしレストランの経営者だったとして、ドイツ人の顧客がついてくれた場合は安心してお店を開けられるなと思うんですよね、なぜならずっと来てくれるだろうと思うからです。一度美味しいと思って来てくれたら繰り返し来てくれると思うので。同じものを作っていれば良いというか、こちらからしたら楽と言えばそうなんですけど。今の職場で20年来の顧客とかいますから。』
一度信用を得ると担保される良さがあるようですね。保守的な食事情の理由は何が背景にあると思われますか?
『最近は外国人移住者が増えて、そういう方々が以前になかった食文化を広げて、ソーシャルネットワークの普及があって、その影響で以前と比べて食事情は急速に変わっていってるとも思います。ここ5、6年は特にバリエーションが増えた印象です。例えば以前ですとお好み焼きってありますよね、大都会で働いていた1990年代はお客さんになかなか受け入れられなかったメニューのひとつだったんですよ。お好み焼きを鉄板の上で焼き始めた瞬間にぐちゃぐちゃに混ぜ合わさってる素材を見て何か汚いものに見えるから食べたくないとか、見た目で判断してしまう。一品だけで勝負するのは難しかったです。当時の日本食レストランは寿司も出すしうどんも出すし天ぷらも出すしとんかつも出すし、要するに色んなものを一軒で提供するスタイルが主流だったんですよ。日本でよくある専門店、一つのメニューに特化したレストランスタイルは当時はほとんどなくて、でもそういう専門店が最近になってようやく少しずつ受け入れられ始めてる印象ですね。』
飲食業界もソーシャルネットワークの影響ありますよね。
『そうですね。日本のサブカルチャーに影響をされて日本食を食べに来るお客さんも結構いて、例えばアニメに出てくる主人公が食べてるものを食べてみたいとか、主人公が食べてるラーメンとかたこ焼きを食べてみたいとか。』
大抵の料理は今だとどの国に行っても先進国では同じものを食べられますよね。それがもっと広がるとやがてその国に行かないと食べられないものは消えて無くなってしまうんですかね。
『確かにローカルの食べ物はだんだん減っていくでしょうね。』
今は料理のレシピがインターネットで手軽に手に入るし、料理はアートだと自負する料理人や、包丁さばきを演出したインフルエンサーがYou tubeに動画を投稿したり、今までになかった切り口で料理に携わる人たちが出てきていますよね。
『私のボスはですね、食をいかにエンターテインメント化するか、見せる料理をいかに作るか、それを大切に考えて料理を作ってますね。私はどちらかというと端でコソコソ料理を作っていたいタイプですが、彼は私とは真逆の性格で目立ちたいタイプで、いつも彼が僕に料理のアイデアをくれるんですよ。例えば食材の相性が悪そうな料理を作れないかと提案してくるんです。初めは私も彼よりは保守的なので受け入れられないんですけど、やっていくと最終的には意外な料理が作れたり発見があったりするんですよ。そういう意味では彼の元で働いてるというのもものすごく勉強になりますし、彼と働くことで固定観念に囚われて料理をしてると出来ないような料理が出来る。そのことは新しい料理を作るためには外国人目線でないと出来ないような発想も必要なんだなと思いました。それをなんちゃって料理って評価する人も中にはいるんですけど、私は美味しかったらいいんじゃないかって思っています。』

食って何なんだろうって考えた時に、生き物として当たり前の欲求と同時に現代では食を楽しむ価値観が当たり前に共有されてますよね、価値観や食文化は社会の変化や技術の進歩によって変わっていきますが、ドイツではどのように変化してきたか教えていただけますか。
『海外の日本食の立ち位置はもっと細分化、専門化していくと思うんですよ。受け入れられる状況ができてしまったことはあるんですけど、ビーガン料理は完全に定着しましたよね。同時にビーガン料理は今後更に細分化していくと思います。根菜のみのビーガン、オボベジタリアン、レッドベジタリアン、ホワイトベジタリアン。例えばレッドベジタリアンは赤身のお肉は食べて良い、ホワイトベジタリアンは白身のお肉と魚は食べて良いとか。調理人としては相当面倒臭い未来が待ち構えてるなと思ってます。細分化するとお客がある食べ物だけを食べたければ専門料理店に行けばいいですし、専門料理店の調理人はそこに特化した知識があれば対応できるので面倒臭くはないかなとは思います。逆に総合料理店の調理人は細分化された食文化に全て対応していかないといけないので大変ですよね。』
健康や環境への関心が食の関心の高まりに繋がっていると。
『食材の表示方法ひとつとっても大きく変わってきていますし、家畜の飼育環境が話題になったりしてますよね。例えば餌に抗生物質が混ぜられているとか、家畜への予防接種の必要性とか、その家畜が消費者の口に入った時にどういった影響を及ぼすかとか。ただ正直調理人の私達には最終的にどういう影響があるかはよくわからないんですよ。家畜の農家に見学に行ったり、そういう論文を読んで理解しないといけないんですけど、出来てないのが実情ですよね。例えば養殖の魚にはワクチン接種があるんですよ。2011年にチリでシャケが大量にウイルスで病気にかかって死んだ事件があったんですけど、その際にヨーロッパからチリにシャケを大量に送って養殖を復活させた出来事があったんですよ。シャケにもワクチン接種してますから。豚に関しては成長を促すためにホルモン投与をしています。ビーガンの方の多くは動物愛護の観点からビーガンになられた経緯があって、ベルリンでも動物に人権をというスローガンのデモをよく見かけますし、人間による動物への一方的な処置を写した動画などが拡散されて、動物の悲惨な現状を見た方がビーガンになられる判断は理解できます。ただ調理人の立場としては動物や植物を調理して商売をしている因果な商売なので、そういう現状に対してものを言うのはすごく難しい立場なんですけど年々食材を取り扱う難しさは感じています。いかに食材を無駄に使わないか、心がけてやってはいますが、自分の中のいい調理人の定義は、美味しいものを作る云々よりもまずはゴミ箱がどれだけ軽いかっていうことですね。食材を使い切る調理人がいい調理人だというのが僕の考えです。美味しいかどうかは、プロなので美味しく作って当たり前なので。』
今おっしゃったような思想はドイツで培われた経験が大きく影響していますか?
『こちらに長く住んでいるのでね、影響はあると思います。例えば日本ではいかに食材を新鮮に保つか、この価値観は大切にされてますよね。いけすに泳いでいる魚を捕まえて、注文が入ったら捕まえてシメてお客さんに提供して、いかに新鮮な食材を食べていただくか。実際はその料理はすごく喜ばれると思うんですよ。ただ今の僕はあのスタイルに対しては確かに抵抗感はあります。ドイツに就職する前に日本の魚屋で働いていて、そのまま日本のレストランに就職していたとしたら、いかに食材を新鮮な状態で提供するかってことに注力してると思うんですよね。日本は動物のと殺の仕方やシメ方の技術はドイツに比べて発達してると思うんですよ、身が生きたまま美味しく熟成していく神経ジメは典型です。血液だけ抜いてシメて置いておく。そういう日本の技術は素晴らしいと思いますし、日本の食文化に特化した技術ですよね。でもそれには少し抵抗感があります。もちろんこちらでも生きたオマール海老をそのまま熱湯で茹でる調理法などはあるんですけど、調理人の立場でいながら生きたままの食材を調理する時はかわいそうだなって思うんですよ、海老を見ながら。罪深い商売だなって認識しながら働いてます。』
ドイツでは一般的に新鮮な魚は手に入りにくいですよね。
『実際にドイツでも新鮮な食材を喜んで頂くっていう流れはあって、その価値観が以前よりも共有されていると感じますし、日本食は流行っていると思います。ドイツの食文化と日本の食文化が少しずつですけど混ざり合ってるって傾向はあると思います。』
ビーガン志向の若い人たちがドイツに多いって記事を見ると、世代間で食に対してどういう意識の変化が起きていると考えられてますか。
『肉を食べない人は減っていくと思うんですけど、無くなることはないと思うんですよね。実際ビーガンから肉を食べるようになった人たちも見てるんですよ。思想的にビーガンを始めて結果的に体調を崩された方なんですけど。それは何かというと栄養学的観点からいうと肉を食べる必要があるという判断なんです。例えば僕の妻は結婚までは肉の脂身や食感が嫌いという理由で肉を食べなかった人なんですね。ビーガンではなかったんですが僕が肉を美味しく食べられるよう調理して提供したら食べるようになったんですよ。肉を食べる前までは体が冷えてた、寒いと感じることがあったらしいんですけど、肉を食べるようになってからは体があったまるようになったと言い出していて。体調が以前より良くなったって、変わったって言うんですよ。それは栄養学的観点からカラダに必要な栄養素を摂ることが出来るようになった影響だと考えることができるんです。もちろんビーガンを始めて体調が良くなったっていう人もいるので個人差はあると思いますが、大切なのは肉を食べることが必要な人たちもいますから、ビーガンだけに偏りすぎるのはどうなんだろうと、ビーガンを他人に薦めるのはいいですけど、薦めるにしてもビーガンを過度に強制することはしてはいけないのではないかとは思います。実際にビーガンに転向して体調が良くなった人たちもいるので、思想や健康法を人に薦める行為は咎めません。ビーガンに転向して体調を崩してる人が、要するに思想の為だけに無理矢理ビーガンを続ける行為は僕はお薦めしませんね。自分の体調に合った食事法を取るべきだと僕は思います。』
食に対して正しい情報が共有されてないというジレンマはおありですか。
『検査や規制をクリアした食材が食卓に並べられているというのは分かるんですけど、例えば食材に対してホルモン注射を打ちましょうという新しいルールができた時に、注射を打っている食材を10年20年口にし続けた時に過去のデータがないから安全かどうかはわからないですよね、どういう影響があったかは時間が経過して初めてわかることですから。』
そうなると人間は何を食べればよいのかって問いに行き着くんですけど、ドイツでは食の安全をどう担保すればよいですか?
『僕もいちいち食材を細かく見てるというわけではないですけど、街のスーパーと比べるとお値段は高いですが、ビオ食材を扱っているお店の食材は安全なのかなと思います。ビオだから美味しいということではなくて、消費者はお金を出して安全を買えるって側面はあると思います。ビオの定義は色々ありますが、一定の安全基準をビオ食材はクリアしているのでビオの食材は他の食材と比べて安全だとは言えます。例えばビオの豚肉はビオの餌を食べてるというようなことです。ただ僕の知識が浅いので、ビオの豚が抗生物質を打っているのかは分かりません。仮に打っている場合それがビオの豚という扱いになるのかは分かりません。抗生物質を打たないと家畜で病気が蔓延した時に全ての豚が屠殺されますよね、商品としても出荷されない、世界中で家畜に病気が蔓延すれば地球上で人間が食べる家畜の豚が無くなる。ですからビオの餌を食べてはいますが薬物を投与されている家畜が安全なのかどうか、結局家畜業者も食べていかないといけないから病気が発生しない為の予防として家畜に薬物を投与なきゃいけない、それが現状ではないかと。』

ドイツの食品と化学の関係性について考え方を教えていただけますか。
『食品添加物の量だけ見ると他国と比べてドイツは少ない方ですね。インターネットから得た情報なので正しい情報か定かではないですが、日本では承認されてる食品添加物の種類は約800種類(厚生労働省発表・831品目)に対してドイツで承認されてる食品添加物は約60種類です。』
それほど違いますか。
『こういう仕事に携わってると、ドイツの輸入食品に対する規制が改定された影響で、ドイツに日本から輸入食材が入ってきた時に荷物が止められる現場に立ち合ったりするんですよ。以前は問題なかった輸入食材なんですけど、何で荷物が止められたのか訳を聞くと合成甘味料だったり、保存剤や着色料だったり。日本からの輸入食材で止められるのはアニマルエッセンスっていう、豚の骨から抽出したエキスだったり、スープですよね。こういうものはドイツの検疫で引っかかるので日本からドイツに輸入は出来ないですし食材としても使えないです。ドイツで骨から抽出したエキスは使ってよいですが、日本のラーメン屋がドイツにスープを輸入して使っていた時期があって、以前は問題なく使えてましたが今は引っかかりますね。』
ドイツでは食への安全性はある程度担保されてると思いますか。
『例えば過去10数年間でスーパーで購入した食材を食べ続けて具合が悪くなった経験はありませんし、ある程度担保されてるとは思います。ただ同時に神経質になり過ぎないってことも大切でそれが一番健康にいいのかなって思いますね。』
ドイツで実際に料理される際、日本の食材とはどう向き合われていますか?
『ドイツで日本食のレストラン経営をしてる同業者がいますよね。結局どこも日本から食材を仕入れる業者は同じになるんですよ。ですから結局使ってる食材もほぼ同じになる。キッコーマンの子会社のJFCかSSPだったり、最近新しく出来た輸入業者JFEだったり。醤油ひとつとっても同じ醤油を使うことになるので同じ味になる。ですから味の差別化に工夫はしますよね。例えば醤油に鰹節を入れたり昆布を入れたり味醂を入れたり、寿司酢ひとつをとってもいい酢を使って自分達で調合したり、細かいところで差別化をはかったりしますね。 A のお米はBのお米より値段は安いけど、食べ比べると味はほとんど変わらないとか。小さな工夫を積み重ねていけば最後は大きな差になると思うんですよ。他所が使ってない食材を使ったり、発注ルートを自分達で開拓したり、実際にスペインに行ってマグロを仕入れたり。』
意地悪な質問をしますが、ドイツでは食べ物といえばソーセージとじゃがいものイメージが根強くあると思うんですけど、それについてはどうお考えですか。
『ドイツの食材はじゃがいもとソーセージっだっていう日本人の発想は今やもう古いと思いますね。ドイツには他にも美味しいものがたくさんありますし、イメーじは更新するべきじゃないかと思います。ドイツ料理そのものをレベルアップさせようと奮闘している若い調理人たちは増えているんですよ、例えばドイツ料理をフレンチっぽく提供しようとしたり、イメージを変えようと情熱を持って取り組んでいる料理人は実際にいます。そういう料理人が作った料理は美味しいです。実際にそういう料理はじゃがいもとソーセージではないですし。先ほども言いましたが食に対してドイツ人は他の国の人と比べて少し偏りが強いと思うんですよね。例えばビールの種類ひとつとっても五千から六千種類あったり、ワインもたくさん種類があるんですが、ビールやワインに対する執着と同じぐらいの情熱を食にももっと向けて欲しいなとは思いますね。残念なことに実際街のドイツ料理レストランに行ってみるとメニューに書いてる料理は大体メインで五、六種類で、どこのレストランに行っても似たようなメニューが多くて、どれを食べても大体どこも似たような味でレストランによって味の違いもそれほどないんですよ。僕はドイツ国内旅行が好きで、地方都市に行って地ビール飲んでドイツ料理を食べる旅行をするんですけど、ドイツの地方都市に行くと二十年以上前のドイツ料理のスタイルをそのまま続けてるレストランを見つけるんですけど、ドイツ料理のレストランなんだけど、ピザも置いてるしポテトもあるしハンバーガーもあるしってスタイルのレストランで。これは僕の想像なので偏っていますが、こういうレストランを見てると色んな料理を取り込んだ結果、メニューに表れてるようにドイツ料理に誇りを持てなくなってるのかなって少し偏った見方をしてしまうことがあって。ですから地方都市に行ってピザもハンバーガーも置いてない品数の少ないドイツ料理一筋で頑固に経営してるレストランに偶然に巡りついりすると嬉しくなりますね。』
僕がドイツの地方都市で見たレストランで印象に残っているのはシュネル・シュニッツエルなんですけど、注文したらすぐにシュニッツエルが出てくるスタイルで、シュネルがお店の看板になっていて。
『ドイツにはインビスっていう食文化があるから、シュネル・シュニッツエルは受けると思うんですよね。日本でいう立ち食い蕎麦的なものですよね。これは僕の持論なんですけど、ドイツ料理は改良、工夫の余白がまだまだあるって僕は見てるんですよ、サービスひとつとっても改良、工夫の余地がまだあるって。』
食べることへの興味と同時に手に入る食材で食文化を形成するので、地理的な環境が食文化に影響する当たり前の話はありますよね。日本は海に囲まれた島国でドイツは地続きの大陸の中にある。
『日本人は食べることに対して他国に比べて執着心は変態的だと思います。日本で調理人をやらなくて良かったなって本当に思います。』
なぜですか。
『厳しい世界ですし厳しいニーズに応えられなくなり調理人を続けられてないなと思います。日本の調理師学校の先生に聞いた話なんですけど、日本では調理師学校の卒業生の七割が調理人を続けられず辞めていくそうです。アイデアひとつで成功しそうに見える業種ですし、他の業界に比べて敷居はどちらかというと低い業界ですけど、実際調理の現場や労働環境は厳しいです。』
私はその七割の人間の側だったんですけど。
『僕は調理人という仕事は絶対に誰にも薦めませんね。自分に仕事があって趣味が講じて料理をやる人は試しに一度やってみたらいいと思うんですよね、隣の芝生はよく見えるじゃないですけど、気持ちはわかるんですよね。僕は料理をやりたくて調理人になったわけではないので、好きなことで食べていけて子育ても出来て好きなことが仕事になっている人は羨ましいなって思います。好きこそものの上手なれって言葉がありますけど、下手の横好きって言葉もありますよね、いくら好きでも上手くなれないものもあると思うんですよ、こっちの人の方が多いと思うんですけど、なんとかできることを仕事にしてそれが人から望まれる、それを仕事にした方が幸せになれると僕は思うんですよ、無難な幸せと言いますか。今となってはもう何が好きだったか忘れちゃいましたけど、実際調理人の仕事は辛くてキツイですけど、幸せはプライベートで求めるようにしていて、仕事はあくまで食べていく手段として考えていて、料理に携わっているのはお店で必要とされているから続けてこられたという感じです。』
嫌いな事でも続けていると愛着が出てくる。
『自分でいうのもおこがましいですけど、自分としては作るからにはつまらない料理は作りたくないという思いはあって、その判断基準は作った料理を自分が食べたいかどうか、その判断基準は同僚が作った料理にも使うんですけど、僕が今の職場で必要とされてる理由の一つは、それが信念というのかどうかわかりませんけど、それを信念というならその信念を買ってくれてるんだと思います。料理に対して好き嫌いでない判断基準というか、自分なりのルールがあるかどうか。例えば僕が作る料理が雇っている方のイメージを超えてた場合、必要とされると思うんです。正穂がいればなんとかなる、正穂がいてくれたらいい料理が出来る、僕が必要とされてると感じることができる雰囲気があると嫌な仕事でも続けられるんだっていうのはあります。過去二十年はまさにそうでしたし。』

ドイツで調理人になられていないとしたら実際何をされていたと想像されますか。
『おそらく僕は他の仕事についててもモノを作る仕事についてると思うんですよ。おそらく食器作ってますね、多分、器ですね、陶器です。ドイツで料理を作るのが本当に嫌になった時に一度陶器作りについて調べたことがあるんです。日本に帰って陶器を作るところに弟子入りしようかなって考えた時があったんですね。』
ドイツで暮らしていく上で私たち外国人が手っ取り早く仕事につける業種に飲食、サービス業があると思うんですけど、その業種に長年外国人として携われてこられて、労働環境の変化や実際の現場でどんなことを見てこられましたか?
『例えば中華料理屋で働いてるベトナム人ですけど、彼は自分で賃貸契約が出来ない、滞在するための書類を集められないような人達と同じ境遇で、それでもドイツに来てる。要するに不法入国者、不法滞在者なんですけど、それでも食べていかなきゃいけないから、本国に仕送りするとか、人生一発逆転を夢見てリスクをとって外国に来てるような人達ですよね。彼は中華料理屋の地下室で寝泊まりをして働いていましたけど、そういう状況の労働者や調理人は居ましたし、それを平気で続ける経営者も見てきました、それは今でもあるしそう言う奴隷制度のような環境は見てきました。』
それは私も聞いたことがあります。酷いですよね。
『日本人に関してはドイツが好きで滞在したくてビザを取得したいと考えた場合、日本食のレストランにまずは就職してそこで就労ビザを発行してもらう、それが一番早いのかなと思います。基本的に日本食のレストランの多くは日本人を必要としていますし、日本人が必要な職種と考えると他の業種に比べて飲食は一番就職が決まりやすいのかなとは思います。アーティストビザの取得は簡単に取れるものなんですか?』
年々難しくなってると思います。ドイツは移民難民が増えすぎた問題でビザ取得自体以前よりルールが厳格化されてる。
『1990年代当時はドイツに滞在する日本人がビザ取得の方法としてまず日本料理レストランに就職する経路が当たり前にあったんですよ。今はそれがどこまで残っているか分かりませんが、日本料理店で働く外国人も少しづつ増えて、日本人以外のドイツ人や異文化人が作る日本食の技術は上がっていて、年々異文化人の日本料理調理人は増えていますし、異文化人が経営する日本料理のレストランも増えました。今後は人種に拘る必要もなくなってくるんじゃないかと思うので、日本人が日本料理レストランでビザを取得するのは今後難しくなってくるかもしれませんね。』
単純に日本料理のレストランで働く日本人の大多数は、生活の為に調理人をやっている人が多いように見えますが、最初から知識や技術があってレストランを経営する目的で調理人をやっている人もいますよね。
『日本のサブカルチャーに興味を持つドイツ人や異文化人が年々増えてると実感しますし、日本に行ったことがないのに独学でラーメンを研究してベルリンでラーメン屋を始めるドイツ人がいたり、食に関しては国境が消えつつあるって感じはしますね。実際に異文化人で美味しい日本料理を作る人多いですよ。僕が働くレストランの同僚もドイツ人、ベトナム人、タイ人、トルコ人、ロシア人、イスラエル人と多国籍です。美味しければどこの国の人が日本料理を作ってもいいと思うんですよ。』
外食産業としての日本料理はドイツではポテンシャルがあるように見えますが。
『日本料理レストランはこれだけ増えているので、知識と技術を持ってしかも調理師免許を持っていればどこでもやっていけると思います。ドイツでは日本料理の需要はこれからも増え続けると思いますね。』
最後に読者にメッセージはありますか。
『はっきり言って何の目的もなくドイツに来て30年が過ぎたんですけど、僕にとってドイツは日本で生活するより合ってた、そういう国でした。あくまで僕の経験からですが生活するところを考える際に日本に住んでいる人は日本だけに限定して考えるのではなくて、もし日本で生活していて生きづらいなと思ったら海外に目を向けてみるのもいいんじゃないかと思います。僕はラッキーなことに料理を通じて世界を知る事ができましたが、チャンスがあれば数年でもドイツや海外に移住する経験を積むことは、いいことではないかと思います。日本に住んでいたら知り得ないような異文化に触れる事ができますし、そういう経験は偏見や差別を無くすことにつながるのではないかと思います。』
ドイツ料理のイメージは変わると思いますか?
『僕は将来アップデートできると思います、それを信じたいです。若い調理人達にこれから頑張ってもらいたいと思っています。』
ドイツと言えばソーセージとじゃがいもは古いという考えをお持ちの渡正穂さん、ドイツ料理にはイメージを覆せる余白があると見られているようで、日本料理の魅力は異文化人によって今後広がり続けるだろうという考えをお持ちのようです。
好きではないと言いながら料理へのこだわりを熱っぽく話してくださる姿が印象的で、顧客や同僚からなぜ慕われるのか、それが理解できたような気がしました。
今では何が好きだったのか忘れたという渡正穂さんにこれからも勝手に注目していきたいと思っています。