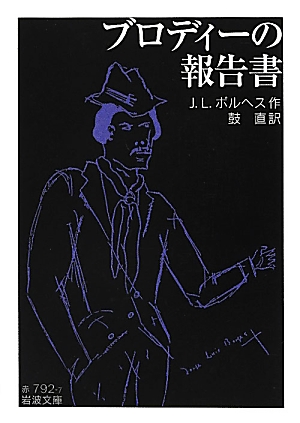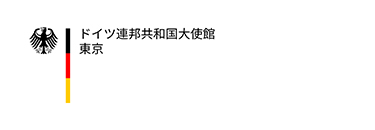映画『パリよ、永遠に』:パリ解放を描く究極の心理劇!

第二次世界大戦終盤。
ヒトラーから「パリを死守せよ。もし撤退するなら徹底的に破壊せよ!」と厳命を受けたパリ防衛司令官フォン・コルティッツ将軍のもとに、パリ駐在スウェーデン総領事ラウル・ノルドリンクが現れる。
ノルドリンクはコルティッツに直言する。「あなたが行おうとしていることは人類史的な誤りだ。理性ある人間の振る舞いとはいえない。相手が総統だろうがなんだろうが抗命すべきです!」
コルティッツは応える。「そんなことはわかっている。だが、私は妻と娘を人質に取られているのだ…もし君が私の立場だったら、いったいどうするかね? パリを救うために家族を見捨てるのかね…?」
連合軍の進撃により刻々と迫るパリ破壊期限。
コルティッツとノルドリンク。ともにパリを愛していながら対決せざるを得ないふたり。
果たしてコルティッツの「究極の選択」はどう決着するのか? そしてパリの運命は!?
…といっても、けっきょくパリがどうなったのかは現状ご存知のとおりなので、そこがドラマの焦点ではありません。
映画『パリよ、永遠に』の見どころは、ふたつの理性の激しい駆け引きと葛藤です。この心理劇の重厚さが圧巻。もともと舞台『Diplomatie』を映画化したものという経緯が色濃くうかがえますが、それにしても主演両名(ちなみに彼らは舞台でも同じ役を演じている)の雰囲気・存在感・説得力、そしてフォルカー・シュレンドルフ監督の入魂の絵造りが凄い。素晴らしい。これはオススメですよ皆様!
本作は、究極の板挟みストーリーです。
中でも、コルティッツが絶望そして怒りとともに放つ「もし君が私の立場だったら、いったいどうするかね?」という言葉は、パリ解放という史実的テーマにとどまらない普遍的な重みと深みを持ちます。つまりその芯には、退路を閉ざされた理性が、非理性に屈しない道はあるのか? という問いかけがあり、これはローカルな意味でもグローバルな意味でも、今なお多層的に問われている問題だからです。
ノルドリンクがそのコルティッツの問いに充分応えたか否かについては、議論の分かれるところでしょう。
そして、もし「応えていない」にもかかわらずコルティッツがパリを救う決断をしたのであれば、それ自体が理性の本質というものを考える材料になるともいえます。
本作はこのような味わいをもつ映画です。史劇性だけでなく、観る人ごとの問題意識に感応する奥行きがある作品です。
自分が強く印象を受けたのは、全体として悪なシステムに身を置きながら、個人としてその自覚を見失わず、ここぞという肝心なポイントで理性の力を発揮することの重要さについてです。そして、ホンモノの理性的決断のアシストには真摯かつ適量のウィットが効力を持つらしい、ということも。
そんな必見映画『パリよ、永遠に』は、2015/3/7(土)から全国で順次公開。ぜひご覧ください!
********************
ときに、パリ解放をめぐるドラマにはいろいろな虚実・裏表があります。
ゆえにガチで詳細な史実研究に照らし合わせると、この映画で描かれるアレコレにもツッコミどころがあるわけです。が、本作の本質は史実をベースとして人間心理の深層を掘りぬく抽象性にあると思われるので、そういう重箱隅じみた指摘は野暮というものでしょう。
代わりといってはなんですが、自分がこの映画を観てかき立てられた思考は以下のとおりです。
【1:パリはワルシャワとならず】本作の冒頭でワルシャワ破壊の映像が流れます。古都ワルシャワ壊滅はナチスの蛮行の悲劇的な実例です。しかしパリは助かった。そして気になるのが、パリを救うにあたって、
「ワルシャワの悲劇を繰り返してはならない」
ではなく、
「ワルシャワと違ってパリは真の西欧文化都市だから破壊してはならない」
という認識が当時のドイツ人にかなり色濃く存在し、さらにフランス人がそれに(意外なほど屈託なく)賛意を示している点です。名作『パリは燃えているか?』にもそういう微妙な描写がありましたね確か。
それが時代性の真実だといえばそれまでかもしれませんが、独仏和解の成果であり象徴、としてこの映画や『シャトーブリアンからの手紙』が賞賛される一方、ポーランドを中心とした東欧との間では今なおわだかまりが重く残る事実、その根深さを再認識せずにはいられません。
ドイツ一国の問題にとどまらない、文化ブロックとしての「東西」対立の解消は必須ながら険しい課題です。それが文芸作品や映像作品にどのように反映されてゆくのか、今後の展開が気になるところです。
【2:邪神の本質】
本作中、「暗殺未遂事件後のヒトラーが廃人同様になっている様を見て、もうこの体制はダメだと悟った」とコルティッツ将軍が語る場面があります。それは大きな説得力を持つ言葉です。そして、あくまで伝統的な知性・理性・教養にもとづく評価です。
そんな状況下、なおもヒトラーを盲信して忠誠を誓い続けるのは獣的な与太者である、という色づけが作中のSS連絡将校の描写からもうかがえるのですが、さて、それで完了扱いにしてしまってよいものか否か?
もちろん本作の主題からはいささかずれる話であり、あくまで別件として扱うべき事案ですけど、たとえばボルヘスの『ブロディーの報告書』的な方向性でアプローチすると、暗殺未遂事件後のヒトラーこそ、「非理性の神」としてむしろ完全体に近づいてしまった、と言えなくもないわけです。
当時そういう認識を持っていたナチス上層の「中の人」が居ないとも限らない。
というか実は居たんじゃないか? そしてその価値観はどのようなものだったのだろう? とダークな想像力が刺激されたりするのです。
しかしまあ、そういう作品はドイツ大使館・ゲーテインスティトゥート推薦扱いには絶対ならないでしょうけど…(笑)
ではでは、今回はこれにて Tschüss!
(2015.3.1)

© マライ・メントライン
マライ・メントライン
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。


![By Jack Downey, U.S. Office of War Information [Public domain], via Wikimedia Commons](http://young-germany.jp/wp-content/uploads/2015/03/Champs_Elysees-edit.jpg)