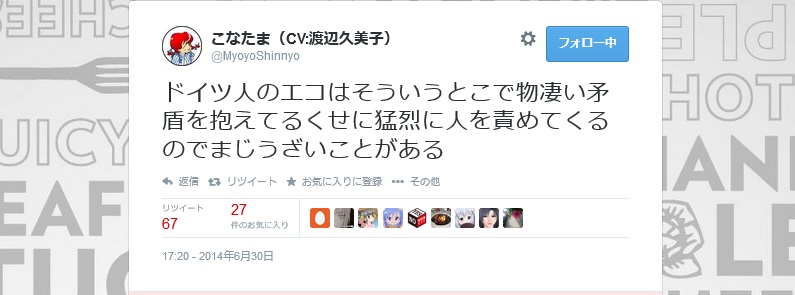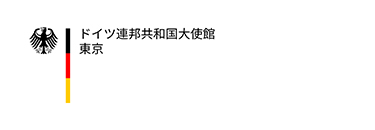大いなる矛盾には、大いなる直視を!

いま(2014年9月時点)、国際世論をそこそこ賑わす話題のひとつに、「脱原発+再生可能エネルギーシフト」を志向するドイツのエネルギー政策をめぐるゴタゴタがあります。ご存じない方は、「再生可能エネルギー法+ドイツ」の検索語でググってみてください。
要するに、「脱原発とか言いながらフランスの原発電力を買ってるのはいかがなものか?」「いやそれは原発推進派によるデマだ!」「でも褐炭火力発電が増えて大気汚染悪化なんでしょ…」みたいな議論が続いているわけです。
このへんに関し、ドイツ関係の話題等でかねてから刺激的な情報発信を行っているこなたまさんが、先日こんなツイート↓を発していました。
 立場的に当然のことながら、ドイツの公的機関・権威機関はこのような意見を完全スルーいたします。しかし私はしない!
立場的に当然のことながら、ドイツの公的機関・権威機関はこのような意見を完全スルーいたします。しかし私はしない!
なぜというに。
個人的に、この「うざい」という感想はすんんんんんごくワカるんです。たとえばエコ政策のつまずきを指摘されたとき、そのドイツ人が、
「いやー、正しいと信じたことを積み上げていったら、いつの間にかでっかい矛盾が生じていた。今さらリカバるのは大変だけど、いろいろな意見を聞きながら技術と政策を磨いて、なんとか将来の落としどころを見つけたいと思うよ」
みたいな姿勢を示したら別に問題ないと思うんです。そうではなく、得てして、
「それはプロセスの中でもともと発生するはずだったことで、マクロな視点から見たら当然計算の内だ。君たちは近視眼的にしか考えられないから概念的なイメージをつかめないかもしれないが、(以下略)」
みたいな話をむしろ威張りながら展開する。そこがウザい。
要するに、「矛盾を隠すための過剰・邪論」を厭わないんですね。私みたく、ドイツ的なものに疑問を感じるドイツ人にとっては、極めて遺憾な情景です(笑)
そして実はこのストレスは、前回記事で私が後半に提起したモヤモヤ感とつながりがあります。
『沈黙を破る者』という小説に私が疑問を持ったのは、「特殊の一般化はどこまで許されるのか?」という問題意識からです。作中人物がクライマックスに見せる、「ヒロインに対する片思いの愛情がゆがんで極大化したゆえに」冷酷に捕虜殺害してしまった、という行為は、それ以前のもっと巨大で一般的で重要な何かから眼をそらすための仕掛けになってないか? あるいは凄い勘違いがそこにあるのでは?
 つまりあの小説は、戦後ドイツ人に突きつけられた
つまりあの小説は、戦後ドイツ人に突きつけられた
「彼はとても良い父親だった。しかし同時に冷酷な収容所看守でもあった」
という深刻な矛盾命題に対して、根拠はどうあれ、巧妙かつ間違った内面的解決を示唆しているように見えるのです。そこで、
そうか、ドイツ人はあの戦争を、ナチズムを反省していない!
やっぱしドイツは偽善国家だ!
…と言いきってしまうと、それは単なる2ちゃんねらーです。それ以上の進化の道を閉ざされた生き物になってしまいます。確かにドイツ人には免罪符を欲しがる深層心理があるかもしれない。しかしそれだけですべてが説明可能とも思えません。ではいったい何なのか? 何があの責任回避っぽいドラマ展開を招いたのか? 個人的な見解を率直に言わせていただくと、それは、
日常的な言語で説明可能な境界線がそのへんにあるから
ということになります。
実はそこがナチ問題の特異点のひとつであり、同じ「矛盾の踏み倒し」にしても、エコ問題議論よりも根が深いことがうかがえます。
ナチズムという現象は、どう論理的に凝った説明を加えても、どこかに言語化不可能な盲点が残る気がします。異界的と表現してもいいでしょう。その「異界」に分け入って価値ある一般論をつかんで来れた人物が、たとえばエーリヒ・フロムやヴィクトール・フランクルなのです。
しかし誰もがフロムやフランクルになれるわけじゃない。だからこそ…『沈黙を破る者』のような存在が必要となるのです。大多数の人に日常感覚的な一定レベルの納得感を与え、安眠できるように。
ただし前回書いたように、「知的なクエストは学究へ、その場の納得感はエンタメへ」という割り切りに私は反対です。学究はその価値を保ちつつもっとオモシロであって欲しいし、逆に、エンタメはそのワクワク感を保ちつつもっと知的であって欲しい。
ということで、エンタメ領域でナチスの核心に迫る場合、それはまず「人間的な矛盾を直視する」ことから始まる気がします。しかし、そんな作品があるのでしょうか?
実はあります。
たとえば、一見無関係っぽいところに。
 フィンランド在住のアメリカ人作家、ジェイムズ・トンプソンの警察小説「警部カリ・ヴァーラ」シリーズは、その容赦のないノワールぶりが賛否両論を呼びながら国際的に評価され、既刊長編4冊のうち2冊が日本でも訳出されています。
フィンランド在住のアメリカ人作家、ジェイムズ・トンプソンの警察小説「警部カリ・ヴァーラ」シリーズは、その容赦のないノワールぶりが賛否両論を呼びながら国際的に評価され、既刊長編4冊のうち2冊が日本でも訳出されています。
その2作目『凍氷』は、ヘルシンキ市内で発生した殺人事件の捜査と第二次世界大戦にまつわるフィンランドの歴史的汚点の揉み消し、この2つのタスクを主人公が同時に任され、いろいろ余計な圧力をかけられながら苦闘する物語です。
ミステリ一般の文脈からすれば「主旋律」は殺人事件のほうで、ゆえに本稿ではそっちは詳述しません。重要なのは戦時中の暗黒面の話です。厳密には一種のネタバレになるかもしれませんが、興醒めにはならないように述べたいと思います。
戦時中、フィンランドは枢軸国側にいたけれどいわゆるホロコースト的な戦争犯罪とは無縁で、それゆえ戦後も国際的に名誉ある立場を維持できた…ということになっているが、実はフィンランド警察とゲシュタポには交流があり、フィンランド国内にもナチの流儀で運営される強制収容所があった! ということをフィンランド国内の歴史家がすっぱ抜き、大騒ぎになって外交問題に発展した、というお話がまず語られます。
…それって基になる史実があるのか? 相当疑わしい話だけど、まあそこに言及すると終わらなくなるので先を続けます。
フィンランド政府にとって都合の悪いことに、収容所の拷問者として名指しされているのは冬戦争の国民的英雄(存命中)だった。そこで政府は巧妙に茶番的な「捜査」を行い、「あれはひどい誤解でした」と公式発表を行うなどしてうまくスキャンダルを切り抜けようとする…なぜ主人公カリ・ヴァーラ警部がその「茶番捜査官」に指名されたのかというと、公式には伏せられているものの、実はヴァーラ警部の祖父(故人)もその収容所の拷問者として名前が挙がっていたからだ!
…なんと大胆な設定でしょうか。さすがアメリカ人です。物議かもしまくりというのも納得です。ちなみに主人公が対峙する「英雄」ラハティネン氏は、メフィストフェレス的な逆説道徳の魅力に満ちた男で、たぶんラウリ・アラン・トルニを参考にキャラクター造形されています。ただし作中、彼自身がトルニについて言及する場面があるので、いちおう別人という設定のようです。
 ヴァーラ警部は殺人事件の捜査をしているときも、常に「大好きだったオレのじいちゃんは、実は拷問者、虐殺者だったのか?」という疑念に延々とらわれ続けます。強烈な焦燥、強烈なストレスです。
ヴァーラ警部は殺人事件の捜査をしているときも、常に「大好きだったオレのじいちゃんは、実は拷問者、虐殺者だったのか?」という疑念に延々とらわれ続けます。強烈な焦燥、強烈なストレスです。
このような物語の場合、普通はその祖父の潔白が証明されて主人公の心の荷がおりるのが相場です。が、
まるでそういう場面は無いまま終了しました。
殺人事件やら外交問題の揉み消し工作が(物語としては当然のごとく)強引ながらうまく解決される傍らで、「オレのじいちゃんは善人だった。そして同時に拷問者、虐殺者だった」という矛盾だけが何のフォローも無くしっかり残る、という凄いオチでした。
厭なリアルだ。しかしこうでなければ。
ここから本質が起動する!
本作はたとえばナチス組織の描写でも、収容所管理組織と武装親衛隊を必要以上に混同しているなど問題ありありなのですが、そんな欠点を軽く吹っ飛ばす根本の一撃を放つ一冊です。傑作です。
ナチ関係作品としては、これぞ次の思考ステップへとつながる! と断言できる内容です。そのように受容できるかどうかは読者次第でもあるのだけど。
しかしただひとつ、大きな問題が。
実は本作の著者ジェイムズ・トンプソン氏は、つい先月の2014年8月2日、不慮の事故で亡くなったそうです。もちろんミステリ業界的に、「これからもっと期待される有望作家だったのに…」と追悼されておりますが、本稿の文脈的にはそれどころではない。なぜ逝ってしまったのだ…!
謹んでご冥福をお祈りします。
しかし納得できない。何故だ。残念すぎます。
ジェイムズ・トンプソンなくしてこの探究には先があるのか?
…よく考えたら、実はあります。なのでこの考察は続きます。
ただし、あまりナチスがらみの話が連続しすぎるのもなんなので、ひとつおいて次回、ということになる可能性が高いです。
ではでは、今回はこれにて Tschüss!
(2014.9.8)