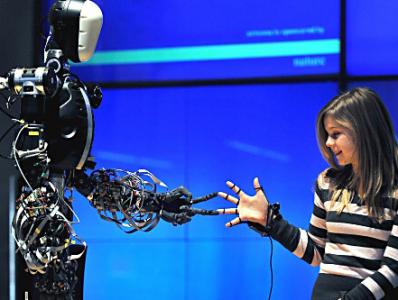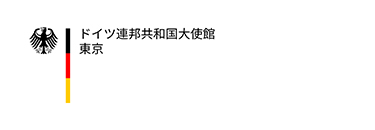ベルリン警察ミステリ、「ドイツ真打」の登場!

ワイマール期ベルリン刑事警察を舞台とするフォルカー・クッチャーの「ゲレオン・ラート警部」シリーズ。ドイツ趣味的にかなり必見な作品です。
本作は、日本版の出版以前にミステリマガジン誌の「洋書案内」コーナーに自分で紹介記事を書いたこともあって(その意味ではノイハウスの『深い疵』も同じだが)、けっこう思い入れ深い作品だったりします。
ミステリマガジン誌に書いた内容を繰り返すのもナンですけど、避けて通るわけにもいかない。とりあえず要点をまとめると以下の通りです。
・ 「魔都」ベルリン! それも大戦間の微妙な時期というのは小説の題材としてかなり魅力的で、これまでにも数々の傑作サスペンス作品の舞台になってきた。
・ しかしベルリンという「食材」をきちんと料理しつくすには、作家に並でない力量が求められる。そのせいか、この領域は伝統的に英米作家の独壇場であった。ベルリン警察系ミステリについてもフィリップ・カーやジェフリー・ディーヴァーといった名が挙がる中、ドイツ作家はまるで影が薄かった。
・ しかし昨今のドイツミステリの質的な向上の中、ついにこのイタい空隙を埋める作家が登場した。その名はフォルカー・クッチャー!
・ クッチャーの作品は、ドイツ人も納得の「ドイツ的感覚」描写とリアリティ、フェティッシュなまでの「ベルリン愛」に満ちていて、かつサスペンス小説として世界的に一流として通用するヴンダバーな内容。今後のシリーズ展開でドイツ警察ミステリのベンチマーク的存在になることは確実なので、皆様乞うご期待。日本版の訳出が待たれる。
で、ついに出たのですよ 日本語版 が。それも酒寄進一さんの翻訳で。
なので、さらに遠慮なくオススメ・ご紹介できる環境が整った次第です(笑)
ゲレオン・ラート警部シリーズ第1作『濡れた魚』は、1929年のベルリンを舞台に、運河で発見された「身元完全不明」な変死体の正体を追いながら展開する迷宮ドラマです。当時のベルリンの表裏に渦巻く魑魅魍魎な各勢力の思惑にもみくちゃにされながら、主人公はしぶとくしつこく事件に食い下がります。
1929年といえば、ナチス党もまだブレイク前のインディーズ政党だった時期。そのころドイツ社会の視線は、いまだ第一次大戦やロシア革命の余波に揺れていた。次にドイツの天下を握るのは、おそらくイケイケ絶頂状態の共産党なんだろうな…という、これまであまり描かれなかったワイマール期の空気感の中でドラマが進行します。これは歴史趣味的にもなかなか新鮮な味わいです。
ナチスが「巨悪」たりえない環境で設定されるラスボスの正体は何なのか? 読者の関心は大きくこの点に注がれるでしょう。そしてクッチャー先生、実に見事で重厚なオチを用意しています。ミステリ通という以上に歴史通を唸らせる、素晴らしき後味の悪さ。そこには、のちの暗黒時代の背骨となる「何か」についての強烈なアピールが垣間見えます。
歴史サスペンスとしての面白さもさることながら、ドイツ人として本作を読んでいて非常に心地よいのが、「英米の作家がステレオタイプ的に描くほどには堅苦しくないけど、英米の作家が好意的に描いてくれるほどにはやわらか頭じゃない」リアルドイツ人の思考や感情表現が、ほどよく読みやすい濃度できちんと表現されていることです。
たとえば作中で展開される会話の中で、「自分はちょっと普通より気が利いた人間なんだよ」ということを身振りでアピールしようとしながらも(表情が全然イケてなかったりして)不器用に失敗するといった、ドイツ人にありがちなイタい生活情景の描写がなかなかツボです。あと、しばしば発生する、警察内での軍隊的・プロイセン的にお堅い報告シーンなどもひそかに外せない見どころです。そう、こういう瞬間こそ、地味ながら「ドイツミステリの味」として内外にアピールできる重要ポイントの一つという気がします。
また、これは最近のドイツミステリ快進撃の原動力だろうと思うのですが、キャラクターの持ち味が非常によい感じです。
主人公ゲレオン・ラートの、生真面目さとテキトーさが絶妙にブレンドされたヴェストファーレン人らしい(つまりベルリン人から見ると微妙にアレな…)性格、しかも場合によって、英米の小説に出てくるゲシュタポ捜査官ばりに冷酷に脅しをかけることも厭わないスタイルはなかなかインパクトがあってよろしいです。じっさい彼はけっこうやることが汚い。ストーリーをキレイゴトで終わらせない作者の度胸の表れでしょうか。左翼思想を持った医師と対峙する場面で、ラート警部は相手の言っている批判が根本的に正しそうだと感じつつ、国家権力の手先としての「卑屈な誇り」にすがって反発しながらその場を切り抜けます。そして微妙に心の中に毒を抱えてしまいます。
なんて素晴らしい内面描写だ。ドイツ作家もついにここまできた!!
また主人公だけでなく、周辺の人々もなかなかよいです。
たとえば法医学者のシュヴァルツ先生。検死官がキャラ立ちしているのは『BONES』など英米の最新サスペンス作品の影響なのだろう(ついでにいえば最近、ドイツでは検死官の体験ドキュメント手記が大人気だったりします)けど、あの陽気で偏屈な時計職人じみた性格は、医学科学の19世紀っぽさと現代っぽさの混淆、橋渡しを感覚的に象徴していて非常に魅力的です。職業的使命感を超えてさりげなく変態チックな領域に食い込んでいる点も併せて、ドイツ、ベルリンという土地柄にうまくハマったキャラクターと申せましょう。
と、そんな逸品なのです。いかがでしょうか!
土地勘を踏まえてストーリーが展開するので、リアルベルリンをご存知の方にとっては特にたまらない内容だと思います。また、19世紀的な街角風景の残照を味わえる点で、「鴎外が歩いたベルリン」みたいな世界をお好きな方にもオススメですね。いろいろな嗜好と接点があるのは、上質な知的エンタメの証明みたいなものです。
本シリーズ、開幕時点では帝政時代の風物や価値観が共産主義と対峙しながら弱体化してゆく状況が背景となっていて、ゴシックロマン的な要素が「最後の輝き」を見せています。そして、すべてが次第に国家社会主義に塗りつぶされていく中で人物たちがどのように悩み、考え、戦い、決断してゆくのか…それが次作以降のストーリーの底流を形づくるのです。一大巨編なのです。
これはもう、読むしかないでしょう!
それではまた、Tschüss!
(2012.09.10)
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)