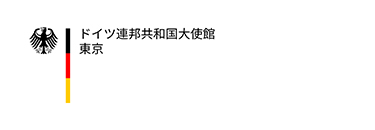たとえば、「いまどきの」ドイツミステリ精髄とは!

いわゆる「ミステリらしいミステリ」を書くドイツ人作家で、現在ドイツで大活躍しており、なおかつ日本でもちゃんと邦訳が出ている(2012年5月時点)人といえば、やはりセバスチャン・フィツェック(Sebastian Fitzek)が筆頭に挙げられるでしょう。
フィツェック作品を特徴づけるのは、精緻に、そして大がかりに練り上げられた「パズル小説」としての技巧感、そして読者を否応なくグイグイ引っ張ってくれるスピード感です。書評家の川出正樹氏が、彼の最新作『アイ・コレクター』(原題:Der Augensammler)について「日本の新本格ミステリ好きにもきっと受けると思う」と述べているのは、特にその前者の要素を受けてのことだろうと思います。
フィツェック作品の邦訳は長らく柏書房から出版されていました。しかし2012年4月、『アイ・コレクター』が海外ミステリ出版の老舗である早川書房から刊行され、前年のシーラッハのブレイクによる「ドイツミステリ」への注目度アップも追い風となり、日本のミステリ業界での評価も上がったように感じられます。ありがたいことです。
『アイ・コレクター』は、ドイツ作家の手になるサイコスリラーの、現時点での到達点のひとつを示す作品といえるでしょう。冒頭に挙げたフィツェック的な特徴を堅持しながら、彼らしいケレン味に満ちた知的情報ギミックが連射されるのです…ただし、『SAW』を思わせる「ジワジワ系」の神経逆撫で描写が激しく効いているので、人情系ストーリーがお好みの方はくれぐれもご用心を。
本作のひとつの大きな特徴は、盲目の異能者(っぽい人物)が登場する点です。もともと科学・医学的情報をベースとしたギミックに並外れたこだわりをもつフィツェックは、徹底的な取材によって「盲人の知覚世界」の奥深さを描きつつ、事件解決のカギを握る「異能」の実在性をめぐって絶妙な論理展開を行います。これはオカルト現象についてよく語られる「ウィリアム・ジェームズの法則」 とも関係する興味深い思索的テーマでもあり、まさにフィツェックの真骨頂といえるでしょう。
実際に読んでいて、ああ、フィツェックらしいな、という以前に「ドイツらしいな」と感じるのは、たとえば英米の作品ならば、「あ、それってグーグルアースを使えばいいじゃないか!」「確かにそうだね~!」といった会話で済みそうな場面で、「私は何故グーグルアースを使うことになかなか思い至らなかったのか!」についての論理的な内面描写、そしてグーグルアースをめぐる社会的・法的問題の概説情報がひとしきり展開するあたりです。
これ、「クドいな」とか「ナニコレ?」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、ドイツ人の思考の内面的な手続きというのは実際あんなものなので、極めてリアルで、しかも何気に比較文化的にも興味深い描写といえるでしょう。
ちなみに本作には、続編『Der Augenjäger』(邦題は『アイ・ハンター』になるかな?)がドイツで2011年に出版されています。『アイ・コレクター』の終幕部を起点に、またも過激なノンストップ・サスペンスが展開します。前作で残された思索的な伏線はどう回収されるのか? また、オカルト的事象に常に立ちはだかる「ウィリアム・ジェームズの法則」を、フィツェックはどう料理するのか…邦訳出版を乞うご期待!
ただしフィツェック自身、『Der Augenjäger』の端書きで、「シリーズ化したこの物語をいつ終わらせるかは、まだ未定」と言明しています。ゆえに読者は、まだしばらくこの循環的冒険譚を満喫することができそうです。シリーズ最後までこのクォリティを維持したまま(いや、できれば向上しながら)突っ走ってほしい…わがままな読者サイドとしては、そう念じずにいられません。
現代ドイツのエンタメ系ミステリは、多かれ少なかれ『クリミナル・マインド』 のような米英の頭脳系ビジュアルサスペンス作品の影響を受けています(受けざるを得ない環境ともいえる)。フィツェックも当然そのうちに含まれますが、「アメリカでひと昔前に流行ったものを今さら追随」という感じではなく、最新の「イケてる」要素をきちんと吸収、自分のものとして消化し、さらにドイツ生活習俗に根ざした独自のアレンジを加えて作品化している印象を受けます。
これは米英作品への単なる追従ではなく、的を射たリスペクトが、結果的に作品の国際的価値の向上につながった例といえるでしょう。
それではまた、Tschüss!
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)