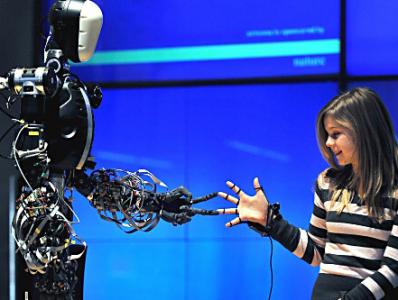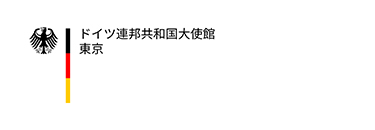「温故知新の」ヨハネス・マリオ・ジンメル!

『白い国籍のスパイ』
この本はすくなくとも、日本語版タイトルと表紙の雰囲気から予想されるような内容の小説ではありません。
「大戦直前の1939年、ある英国在住のドイツ人銀行家が仕事仲間に陥れられ、その結果、彼は列強諸国の情報戦に巻き込まれながら特殊な有能さを発揮してゆく…」などと国際スパイ謀略サスペンス調に書いてみれば、それは確かにあらすじ的にウソではないのだけど、本書の真意の、それこそ万分の一も伝えることにならないような気がします。
本書はまず、本質的にユーモア小説です。部分的にはコメディとさえ言ってよいでしょう。
暴力を嫌い、人生と人間を愛する主人公トーマス・リーヴェンは、運悪くスパイ・軍略家としての天分に恵まれており、それに惚れ込んだ英独仏、各国の軍事情報機関が彼を抱き込もう、利用しようとして虚々実々の駆け引きが繰り広げられます。しかしそのあげく、各国機関は主人公にダマされたり、「平和的に」利用されてしまうのです。主人公は自分の身に降りかかるあらゆるピンチを、たぶん海原雄山も一発で納得するだろう料理の腕と、軽妙洒脱なトークと、セクスィー部長ばりのフェロモンパワーで切り抜けてゆきます。このへんの描写の気の利きかたは、ドイツ語文芸として(恥ずかしながら)かなり特異なものを感じます。作者ジンメルの英国生活の蓄積が活かされている、というべきでしょうか。
主人公に翻弄されてしまう英独仏の各国軍事機関の人物たちは、それぞれのお国柄を反映しながら、みな等しく、ほどよく間抜けでほどよく魅力的に描かれます。普遍的な人間愛の立場からみれば、排他的な国家戦略に奉仕する彼らはみな「敵」となります。が、同時に彼らは良識を秘めた一個の「人間」でもあって、その点をどう刺激して状況改善を図るべきか…というのが、この作品を通しての主人公の課題となっていくのです。
そう、この小説の真価は、実にこの「良識」テーマの引き上げかた、その調理のみごとさにあるように思えます。
謀略・軍事スリラー作品では昔から、「××をつぶせば良識の勝利となるのだ!」という前提条件が勝手に設定されてしまい、その結果、「つぶされてオッケー」となった側の人命は限りなく軽くなります。最近の例でいえば、「イスラム過激組織の秘密アジトを警備するゲリラ民兵」なんかがその最たるものでしょうね。そして、本書の作者ジンメルは、そういった意識構造そのものに敢然と異を唱えます。
たとえば主人公トーマスは、戦時中、紆余曲折のあげくドイツ国防軍に雇われ(というか強引に協力させられ)て、フランスでの対独レジスタンスつぶしを依頼されます。主人公はもちろん絶対的な反ナチです。ここで凡百の作品であれば、主人公は面従腹背でレジスタンス側に情報を流し、その結果レジスタンス側の反撃作戦が成功してメデタシメデタシとなることでしょう。しかしトーマスの場合、それでは解決になりません。
・ ドイツ軍から依頼された軍事的要件を満たし、かつ
・ フランスの対独レジスタンスが誰も犠牲とならず、かつ
・ ドイツ兵も誰も犠牲とならず、かつ
・ 全体的には第三帝国の足を引っ張る
この条件がすべて満たされなければ、やる意味がまったくない! そこでトーマスがとった行動は…というと、いかにも荒唐無稽でおとぎ話的なストーリーが展開されると思うでしょう? 軍事史に詳しい人ならばなおさらです。しかし、作中のドイツ軍とナチス親衛隊の確執の描写をみてもわかるように、ジンメルは詳細に「そのへんの事情」に通じた作家であり、幼稚な展開でガッカリさせられるようなことは絶対ありません。確かに荒唐無稽に見えるかもしれないけど、決して「アンリアル」ではないのです。ではどういう展開かといえば、それはぜひ本書を読んでいただきたい!
しかし、この場で敢えてひとつ申し上げるならば、その「アンリアルでない荒唐無稽さ」は、かのオスカー・シンドラーがユダヤ人を守るため、実際にドイツ当局をダマしおおせた方法にちょっと似ています。要は、「組織が満足する条件」を逆手にとった論理を構築することにあります。そしてそれが真の人倫に沿っていれば、正解なのです。
まっとうな人間として振る舞わなくてはならん。ドイツのまっとうな人物に対して、またフランスのまっとうな人物に対して。裏切者になってはならん。夢想家であってもならん。センチメンタリストであってもならん。ただ人命を救うんだ。
このモノローグが空々しく聞こえないあたりが、本書の凄さです。
一見おふざけのようでありながら、この小説は、「理不尽な巨大体制を個人が覆すのは無理かもしれないが、人間的道理に沿って個人の発想力を磨けば、解釈のつながりによってこの世にもう少しマシな現実を築けるのではないか?」というメッセージを発する点で、おそろしいほど真摯です。そしてその実現のための道具となるのが、ドイツ思考にありがちな「ドグマにもとづいたルールを厳守しましょう」的な剛直さではなく、「やわらかい機知」だったりする点が、実に素敵でカッコイイ。その一点だけでもドイツを内側から超えてます。
神はもっとも期待されていない場所に現れる、という言葉がふと思い出される瞬間です。
思い出すといえば、本書を読みながら、『犯罪』の本屋大賞インタビューで酒寄進一さんが語っていた「世界文学」という言葉を思い出しました。本書は一般にはエンタメと見なされていて、事実そうなのだけど、「世界文学」と呼びたくなる/呼ばせてしまうナニカがあるよなぁ、それは何なのだろう? としばらく考えました。「ジャンル定義を超えたパワー」とか「愛」とか、いろいろな言葉が要素として思い浮かぶのだけど、なかなか思考が決着しない。実はまだ決着してません。その前に締め切りが来てしまった(笑)
1960年に書かれたこの小説は、いまの基準からみるとまったくスピード感が無いし、基本的に性善説だし、時代を感じさせる点が多々あります。ハンニバル・レクター出現以降の、絶対悪がカジュアル化した世界では通用しないような…と言いかけて、いや待てよ、ハンニバル・レクター以降の世界だからこそ逆に真価を再評価できるのかもしれない、という気がしてきました。
主人公トーマスの信念は、実は昭和ヒーロー月光仮面の「憎むな、殺すな、赦しましょう!」というポリシーとまったく同じだったりします。レトロ失笑ネタのように見えながら、実はそれはホンモノの証なのかもしれません。だから月光仮面はなぜかいつまでも消えないのでしょう。同じ理屈で本書も何らかの生命力を維持し、いずれ再ブレイクを果たすかもしれません。
ちなみに酒寄さんも本書が好きで、過日、「Es muß nicht immer Kaviar sein(いつもキャビアがあるわけじゃない)」という原題を活かした訳題が欲しいねぇ、と語っていらっしゃいました。
もし日本語版を再販するなら新タイトルで、もし新タイトルで出すなら新訳版で、などと考えるのは贅沢かもしれませんが、できれば是非!…現行版も、翻訳はけっこう悪くないという話ではありますが。
それではまた、Tschüss!
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。
まあ、それもなかなかオツなものですが。
![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)